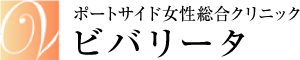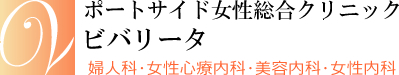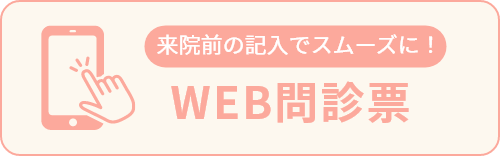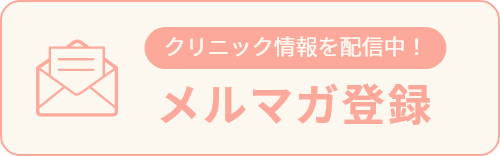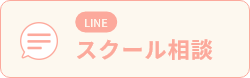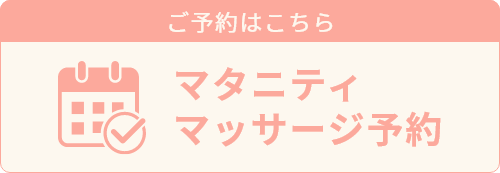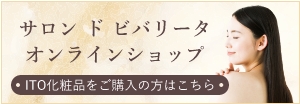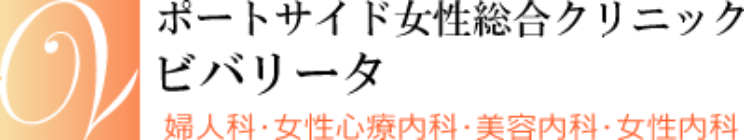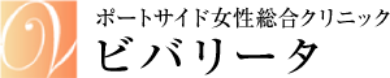婦人科の病気
生理不順おすすめの治療法【横浜駅近く女医のみの診療で評判の婦人科】
どこからが生理不順?(横浜 おすすめ 婦人科 女医)
生理不順(月経不順)は、生理の周期や出血期間が「正常範囲」から外れていることを指します。
正常な生理とは、下記の状態です。
*周期が25~38日の範囲内
*出血期間が3日~7日の範囲内
*生理以外の時期に出血がない
周期が正常範囲より短くても長くても生理不順ですし、ごく少量の出血が2~3日しか出なかったり、だらだら長く続いても生理不順です。
生理の周期が「なんとなく月1回」であっても、1週間以上のばらつきがある場合は、基礎体温をつけて排卵の有無を確認した方がよいでしょう。無排卵であれば、例え周期が正常範囲でも「生理不順」になります。
生理不順だと妊娠しにくい?(横浜市 評判いい 婦人科)
妊娠していないにもかかわらず、3か月以上まったく出血が来ない状態は「無月経」と定義されています。重症な生理不順と言ってもいいでしょう。45歳未満で無月経の場合は、放置してはいけません。
検査で無月経の原因を確認して、適切な治療を行う必要があります。
多少周期が長めだけれど、毎月40日くらいの周期で定期的に生理が来ており、基礎体温をつけると高温期と低温期がはっきり分かれている場合は、「生理不順だけど治療をせずに様子を見ても大丈夫な範囲」です。
生理の周期があまり安定しないな、という場合は、まずは基礎体温をつけて排卵の有無を確認してみることをお勧めします。
周期が24日未満や45日以上の場合や、出血が毎月10日以上続く場合、そして無月経の場合は、婦人科を受診した方がいいでしょう。
特に、長期間の無月経や、無排卵の状態を放置すると、妊娠しにくくなる可能性があります。生理不順だから、妊娠できないわけではありませんが、妊娠しにくくなる一要因にはなりうるのです。
生理不順の原因は?検査は何をする?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
生理不順の原因を確認するための検査は、「超音波検査」と「ホルモン検査」です。
超音波検査は、性交経験があれば膣から、経験がなければ肛門やお腹の上から超音波の機械を当てて、子宮や卵巣の形・大きさを確認する検査です。主に、子宮の内膜の状態や、卵巣が腫れたり多のう胞性卵巣になっていないかなどを調べます。
ホルモン検査は、血液検査でホルモンのバランスを調べます。女性ホルモンの値だけではなく、プロラクチンや甲状腺ホルモンなど、卵巣の働きに影響する他のホルモンも調べます。
生理不順の治療にピルは有効?(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
生理不順の主な治療は、漢方治療・ホルモン治療・排卵誘発です。高プロラクチン血症や甲状腺機能異常があれば、それらのホルモンを正常にするための治療を行います。
生理不順の原因が何なのかを検査の結果から読み取って、生理不順の重症度合い、そして妊娠の希望の有無によって治療法を選択していきます。
大まかな治療の選択方法は、次のような流れになります。
Q:今すぐ妊娠を希望しているか?
している→排卵誘発や不妊治療
していない
↓
Q:卵巣機能がある程度保たれているか?
保たれている→漢方治療
低下している
↓
Q:ピル服用ができない条件に当てはまるか?
当てはまる→カウフマン療法や黄体ホルモン療法
当てはまらない→ピル
今すぐ妊娠は希望しておらず、ピルを服用できない条件(片頭痛や喫煙など)に当てはまらない場合は、一番お勧めの治療法は超低用量ピルによる治療です。
特に、避妊が必要な場合や、多のう胞性卵巣症候群によって生理不順になっている場合は、確実な避妊をしたり、子宮体癌の予防のためにピルを使った方がいいでしょう。
生理不順に対して、産婦人科でピル処方するときの流れは、
*受付時に問診票を記入
*医師による問診(お話し)
*必要に応じて超音波検査やホルモン検査(採血)
*ピルの禁忌に当てはまっていないかの確認
*ピルの飲み方や副作用の説明
*院内または院外処方で薬剤の処方
です。
ピル処方のために内診は必須ではありませんが、生理不順がある場合は超音波検査で卵巣の腫れの有無を確認してから服用した方が安心です。
そのため、ピル処方の流れ的に、「全く婦人科的診察をせずに話だけで処方」は難しい場合があります。
逆に、ピルによる治療が不適切なのは、体重減少によって無月経になっているケースです。体重が減りすぎて、またはカロリー不足によって月経が来なくなっている場合、脳下垂体から出るLHというホルモンが少なすぎる状態になっていることが多いのです。
ピルは、このLHを抑える作用があるので、LHが低くなっている人には使わない方がよいということになります。
同じ生理不順に対する治療でも、原因やその方のベースによって適している治療が異なってきます。
「なかなか周期が安定しないな」「生理不順だと将来不妊症になるのかな」といった不安が少しでもある場合は、一度婦人科で相談してみることをお勧めします。
ご予約はこちら
日付:2026年2月13日 カテゴリー:生理不順
生理不順の治療にピルは使える?【横浜駅近くの婦人科】
生理不順とは?何日来ないと受診?~横浜市 おすすめ 婦人科 女医~
生理不順(月経不順)は、生理の周期や出血期間が「正常範囲」から外れていることを指します。
生理が来てから次の生理までの日数が「周期」です。この「周期」が、25日~38日の範囲に入っていれば、「正常な生理の周期」と言えます。周期が28日の時もあれば35日の時もある・・・という程度のばらつきは、正常範囲内とみなします。
ただし、この範囲の周期で生理が来ていても、1~2日だけの出血で終わってしまったり、少量で10日以上出血が続いたりしている場合は、「正常な生理」ではない可能性があります。
生理が「正常である」と言えるのは、
*周期が25日~38日の範囲内で定期的
*出血が継続する日数が3~7日の範囲内
*1~2日目はナプキンを3~5時間ごとに取り換える程度の出血がある
*生理と生理の間で不規則な出血が起きない
*基礎体温が低温期と高温期に分かれている
といった条件を満たしている場合です。
生理不順の原因は(横浜駅 近くの 婦人科 おすすめ)
生理不順の原因は、卵巣機能の低下や多のう胞性卵巣症候群や体重減少性無月経など様々です。
10代の頃からずっと生理不順です、という方に多いのが「多のう胞性卵巣症候群」です。卵巣の壁が排卵しにくい状態になり、排卵まで時間がかかったり無排卵になる為に、生理の周期がまちまちになります。
ダイエットをきっかけに生理が来なくなるのが、「体重減少性無月経」です。必ずしも「やせすぎ」の状態になっていなくても、ダイエットの方法が体に負担になる方法であったり、体重の減り方が急激すぎたりしても、一時的に卵巣の働きがストップしてしまうことがあります。
特に思い当たる原因もないのに、しっかり定期的に来ていた生理が急に不規則になったという場合は、高プロラクチン血症や甲状腺機能異常など、卵巣以外のほかのホルモンが卵巣の働きを妨げてしまっているケースがあります。
いずれも、「生理不順」という症状だけでは何が原因なのかを判断することはできません。超音波検査で卵巣の形をみたり、血液検査でホルモンの値を調べることで、原因を見つけていきます。
生理不順の治療にピルが有効?(横浜 婦人科 女医 評判いい)
生理不順の治療は、大きく分けると
1)漢方薬を使う
2)ホルモン剤を使う
3)排卵誘発剤を使う
という方法があります。
このうち、3)の排卵誘発剤を使った治療は、「今すぐに」妊娠を希望している方に行う治療です。
なので、妊娠の希望がない方は、漢方かホルモン剤を選ぶことになります。
ホルモン剤の代表が、低用量や超低用量のピルです。避妊用のピルは、低用量のものしかありませんが、治療用のピルはさらにホルモン量を抑えた超低用量のものもあります。
ホルモン量が少ないほど、吐き気や頭痛などの副作用のリスクも低くなりますので、最近では出来るだけホルモン量が少ないタイプのピルを選択するケースが増えてきました。
生理不順の治療にピルを使うのは、次のようなケースです。
*多のう胞性卵巣症候群による生理不順
*生理不順に伴ってニキビなどの肌荒れが気になっている
*受験やスポーツなど生理の日を確実にコントロールしておきたい
*生理不順だけではなく生理痛やPMSも気になっている
*子宮内膜症がある
逆に、ピルを使わない方がいいのは次のようなケースです。
*前兆を伴う片頭痛がある
*血栓症の既往や家族歴がある
*その他ピルの禁忌事項に当てはまっている
*体重減少による無月経
*LHが低値になっているタイプの生理不順
ピルは万能ではありませんが、生理不順も生理痛も過多月経もまとめて改善したい!という場合に便利な選択肢の一つです。
「ピルを飲んではいけない」という条件に当てはまっていなければ、生理をコントロールする方法として試してみてもよいでしょう。
ピルの処方には、必ず医師の診断が必要です。
通常のピル処方時の流れは、下記のような手順になります
1)問診票記入
2)血圧測定
3)医師との面談
4)必要に応じて検査
5)ピルの飲み方や副作用の説明
生理不順で「いつ出血するかわからない」状態を放置するより、ピルでしっかり出血のタイミングをコントロールした方が、生活の質も上がる可能性が高いでしょう。まずは婦人科で相談してみて下さい。
ご予約はこちらから
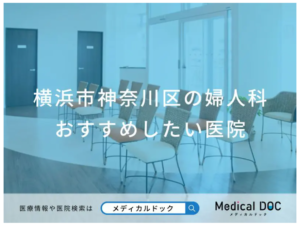
日付:2026年2月13日 カテゴリー:生理不順
妊活中にとった方がいいサプリメント(栄養素) 葉酸サプリは飲まない方がいいの?
★★妊活中はどのような栄養を意識すべき?★★(横浜市 おすすめ 婦人科)
妊活を開始すると、栄養のバランスや生活習慣など、いろいろ気にするようになった、という方もいらっしゃるかもしれませんね。
妊活中の人が意識した方がいい栄養素は、「鉄分」「亜鉛」「葉酸」です。
<鉄分>
「鉄分」は、不足すると鉄欠乏性貧血になります。また、鉄分不足だと妊娠率が低下するため、妊活中には要チェックな栄養素です。
月経がある女性は、毎月血液を失うため、鉄分が不足しがちです。
普通の健康診断で、貧血かどうかを見るときは「血色素(ヘモグロビン)」の値を見ますが、体内の「蓄え」としての鉄分が足りているかを見たい場合は「フェリチン」という項目をチェックします。
実は、血色素が正常でもフェリチン値が低い「隠れ貧血」の人がとても多いのです。
妊娠を望む人の、血中のフェリチンの数値は、どのくらいが適切なのでしょうか?
報告により多少バラツキがありますが、最低でも30ng/mLから50ng/mLは必要という報告や、常時50ng/mL程度以上に維持した方がよいという報告があります。
そのため、妊活中の方は、フェリチンを40ng/mL以上を目安に、鉄分を摂取していただくことが多いです。
食物に含まれる鉄には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。日本人の食べる食材には非ヘム鉄が多く含まれますが、吸収率が高いのは肉や魚に含まれるヘム鉄です。
非へム鉄:
野菜や海藻などの植物性食品に含まれ、吸収率は5%以下と低い。食物繊維や、コーヒー・お茶に含まれるタンニンが吸収を阻害する。
非ヘム鉄が多い食材はほうれん草、きくらげ、プルーン、海草類など。
ヘム鉄:
肉や魚などの動物性食品に含まれ、吸収率は10~30%と、非ヘム鉄の5~10倍も吸収される。
ヘム鉄が豊富な食材はレバー、赤身肉、牛肉、鶏肉、鰹、マグロ、イワシ、煮干し、せんまい、あさりなど。
吸収率の高いヘム鉄を含む食材を、意識して摂取していただくのですが、食事だけでは十分量摂取するのが難しかったりします。
なので、足りない分はサプリメントで補う必要があります。
当院で扱っているサプリメントでも、一番ニーズがあるのが「ヘム鉄」です。
<亜鉛>
亜鉛も、妊娠には重要な役割を持っています。
亜鉛と聞くと、男性の妊活にとって重要な栄養素として思い浮かべる方も多いと思いますが、実は、女性の妊活にとっても大事な栄養素と言えます。
亜鉛は成人の体内に約2g含まれます。成人ではそのほとんどは筋肉と骨中に含まれますが、皮膚、肝臓、膵臓、前立腺などの多くの臓器に存在し、さまざまな酵素のサポートをしています。
亜鉛は、卵胞刺激ホルモンや黄体化ホルモンの働きを高めてくれます。亜鉛が不足すると、性腺機能障害を引き起こし、妊娠しにくくなります。排卵や着床に関係する多くのホルモンに亜鉛が必要不可欠と言えます。
亜鉛は細胞分裂にも関係するので、不足する事で、精子・卵子の細胞分裂にも影響があります。
亜鉛が不足すると、疲れやすい、やる気が出ないなどの「うつっぽい」症状が出ることがあります。
通常の健康診断では、亜鉛の値は見ませんので、病院で採血する際に亜鉛も採血項目に入れてもらうと確認できます。
亜鉛は、カキやカタクチイワシなどの魚介類に多く含まれます。また、牛肉も亜鉛を多く含む食品です。
なので、動物性たんぱく質が不足しがちな食事をとっていると、亜鉛不足になりやすいのです。
亜鉛も、薬やサプリメントで補うことが可能ですが、過剰摂取は弊害が出ることがあります。
補充する場合は、定期的に採血をして、摂取量の調整をしましょう。
<葉酸>
葉酸は、妊活中の方にはお馴染みの栄養素ですね。
妊娠を希望する女性は、胎児の神経管閉鎖障害発症リスク低減のために十分な葉酸摂取(400μg/日)が必要となります。
神経管閉鎖障害は、お母さんのお腹の中で赤ちゃんの脳や背中の神経が作られる途中で発生する、先天的な異常です。発生すると、運動機能や排泄機能に不具合が出たり、命に関わることもあります。
神経管閉鎖障害を予防するには、少なくとも妊娠1ヵ月以上前から妊娠3ヵ月まで、1日400μg以上の葉酸摂取が有効です。
しかし、非妊娠時の 30 歳未満の女性の葉酸摂取量は 300μg/日にも達しておらず、葉酸の摂取源の一つである緑黄色野菜の摂取量も十分ではありません。
葉酸は、水溶性のビタミンなので、蓄積率が低く、とり過ぎる心配はほとんどありませんが、毎日摂取する必要があります。
そのため、厚生省は、妊娠を希望している女性は「普通の食事に加えて」、葉酸を1日400μg摂取することを推奨しています。
つまり、妊娠を希望したら、葉酸のサプリメント摂取は必須であるということです。
もちろん、バランスのよい食事を心がけることは不可欠です。食事に加えて、1日400μgの葉酸をサプリメントで摂取しましょう。
葉酸サプリメントを飲み始める時期ですが、「妊娠1ヵ月前から」摂取するというのは、理論上無理なので、妊活を開始したらすぐに飲み始めるのがよいでしょう。
妊娠3ヵ月までは、摂取し続けるものですから、妊娠中でも飲める成分のものを選ぶと安心です。
日付:2026年2月13日 カテゴリー:不妊症
妊娠検査薬はフライング可能?いつから陽性になる?【横浜駅近くの婦人科】
妊娠超初期にできること・フライング検査はできる?(横浜市 女医 評判いい婦人科)
妊娠を希望している場合、排卵日を過ぎてから次の月経予定日までの期間中は気持ち的に落ち着かない時期になるかと思われます。ついフライングで妊娠検査薬を使いたくなってしまう方もいらっしゃいます。
生理予定日まで待ちきれずに、「この症状があったら妊娠しているかも」という症状に現在の体調が当てはまるかどうかをチェックする方もいらっしゃるかもしれませんね。
ネットでは、「妊娠超初期の症状」というキーワードで検索している方がたくさんいらっしゃいます。「妊娠超初期」というのはネット用語で、医学的に正しい用語ではありません。妊娠が成立したと言えるのは「着床」が成立してからなので、排卵日を過ぎてすぐの「妊娠2週○日」という表現は医学的には矛盾があるのです。
妊娠している可能性を示す症状は、排卵後の胸の張りが強かったり、高温期がいつもよりしっかりあって10日以上続いたり、吐き気などの「つわりっぽい」症状があったり・・・と言われたりしていますが、こういった「体調の変化」は月経前症候群でも見られることがあるので、症状だけで妊娠を推察することは困難です。
1人目の時は高温期の胸の張りが明らかにいつもより強かったけれど、2人目の時は普段通りだったのに妊娠していた、というケースもあります。
「妊娠」の確認は妊娠検査薬で(横浜市 評判いい 婦人科 正月)
妊娠しているのかどうかは、妊娠検査薬で陽性がでるかどうかで確認します。妊娠検査薬は、妊娠組織から出る「HCG」というホルモンが尿中にどのくらい出ているかを見る検査です。
この「HCG」の濃度が一定以上になると、妊娠反応が「陽性」になります。妊娠検査薬の「線」や「印」が薄い時は、「HCG」の濃度がまだ低いけれどわずかながら出ていることを意味します。
生理の予定日から使える妊娠検査薬は、フライングで検査をしたい方に人気ですが、「HCG」が尿中に出ているかどうかを調べていることには変わりありません。少量の「HCG」でも陽性反応が出る、つまり試薬の感度がよいものが「生理の予定日から使える」ものなのです。
生理予定日の1週間後から使える妊娠検査薬は、陽性が出るために必要な「HCG」の濃度が、前述の検査薬より多いということです。
妊娠検査薬はいつから使えるのか?ですが・・・排卵日がはっきりわかっている人は、排卵日から2週間後に検査をすれば、妊娠であればある程度判別できる濃さで陽性反応が出るはずです。
排卵日が不確実な場合は、排卵日と思われる日から2週間後に検査をして、陰性なら3~4日後に再度検査をしてみるとよいでしょう。
妊娠検査薬はフライングで使える?(横浜市 評判いい 婦人科 土曜日)
時々聞かれるのが、「フライングで検査をする場合に最短でどのくらいで妊娠反応は出るのか?」です。
使用する妊娠検査薬の種類によっても異なりますが、生理予定日から使用できるタイプのものだと、妊娠3週5日くらいからうっすらと陽性反応が出ることがあります。排卵日から12日後くらいですね。妊娠3週3日や4日では、市販の妊娠検査薬では反応は出ません。
つまり、フライング検査をするにしても、2~3日のフライングが限界ということです。
妊活中だと、どうしても待ち遠しくてフライングで検査をしたくなる気持ちはわかりますが(私は1人目の時は妊娠3週5日で検査をしました・笑)、生理予定日3日以上前だと妊娠していても陽性反応が出ないことがあります。
結果を見て逆に気持ちが揺れ動いてしまうこともあるので、妊娠検査薬の使用は生理予定日を過ぎてからがよいでしょう。
生理の周期が安定している方でしたら、生理予定日4日後や5日後であれば、陽性反応を確認できます。
ご予約はこちらから
日付:2026年2月13日 カテゴリー:不妊症
生理前のイライラは本当に生理のせい?
「月経前症候群」は生理前だけに起きる不調(横浜 おすすめ 婦人科 女医)
生理前に心身の不調が出て、生理が来るとスッキリ改善する状態を「月経前症候群」と言います。
人によって出る症状は様々で、腹痛や腰痛などの身体症状がメインで出る人もいれば、気分の落ち込みやイライラなどの精神症状がメインで出る人もいます。
多くの場合、生理が来る1週間くらい前から心身の不調が出始めて、遅くとも生理の3日目くらいには一通りの不調が消えていきます。
生理前もイライラするし、生理後もイライラするという場合は「月経前」ではないので「月経前症候群=PMS」とは異なる病気ということになります。
排卵に伴うホルモンの「波」が悪さをして、心身の不調を引き起こしている場合は、ピルや黄体ホルモン剤によって排卵をおさえることが症状の軽減につながる場合があります。
生理前の不調はすべてPMS?(横浜市 評判いい 婦人科)
ただ、月経前に出ている症状が、すべてPMSとは限りません。
生理前の腹痛や腰痛が、実は子宮内膜症による症状だったり、生理直前に出る頭痛が片頭痛の月経周期増悪の場合もあります。
また、生理前の精神症状だと思っていた症状が、実は精神科的な病気の月経周期増悪だったり、発達障害による症状であることもあります。
厳密に「月経前症候群」なのかそれ以外の病気なのかを判別することが難しい場合もありますが、どのような症状がいつ出ているのかを記録したり、精神科的な診察によってある程度鑑別することが可能です。
PMSなのかどうかは「記録」をつけると見えやすくなる(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
気分の落ち込みやイライラなどの精神症状を、「いつ・誰に(何に)対して・どの様なシチュエーションで」感じたのかを詳細に記録して頂くと、それらの症状が「生理のせいではない」ということに気付く方も少なくありません。
ある患者様は、「生理前になると怒りが制御できなくなる」とおっしゃって受診なさいましたが、記録を2カ月ほどつけていただいた時点で、ご自身で「生理前じゃないですね」と気づかれました。その方の場合は、イライラを感じる対象が特定の人物に限定しており、しかもその相手が「何をした時に怒りが爆発しやすいのか」が、記録をつけるだけで客観的に自覚できるようになったのです。
普段からイライラしやすいけれど、生理前に特に「爆発」しやすいという人は、普段から「表に出してはいけない」と思ってしまっている怒りやその他の感情がないかチェックしてみるといいでしょう。
それらの感情を、「生理前だけは生理の『せいにして』表に出せる」状態を作り出していないかを見直してみることをお勧めします。
ご予約はこちらから
日付:2026年2月13日 カテゴリー:月経前症候群(PMS)
生理不順はピルをやめたら元に戻る?【横浜駅近くの婦人科】
ピルは生理を整える作用がある?(横浜 評判いい 婦人科 女医)
生理不順(月経不順)の治療は、大きく分けると漢方薬を使った間接的な治療と、ピルや黄体ホルモン剤を使ったホルモン治療に分けられます。
最近は、保険で使えるピルの種類が増えてきたこともあり、生理不順の改善目的でピルを処方されている方も多いのではないでしょうか?
ピルを飲むと、女性ホルモンがバランスよく補われた状態になりますので、定期的に出血が来るようになります。そのため、生理の周期を整える方法のひとつとして、ピルは有効です。
また、多嚢胞性卵巣症候群や排卵障害で、ホルモンがアンバランスになっていた場合は、それらを整えてくれる作用もあります。ピルの種類によっては、男性ホルモンを抑える作用もあります。男性ホルモンが高くなりすぎている場合は、その影響でニキビや多毛などの「男性化兆候」が表れることがあります。男性ホルモンを抑える作用があるピルは、それらの症状の改善も期待できます。
ピルは排卵を改善させる?(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科 土曜日)
ピルを服用している間は、排卵は抑えている状態になりますので、厳密な意味で「排卵を促す治療」にはなりません。
ピルで排卵を抑えることで、一時的に卵巣をお休みさせてあげることができるので、ピルをやめた後の排卵が起きやすくなる可能性はあります。
よく、「ピルを飲んでいれば生理は来るけれどピルをやめたら生理不順になるので、ピルは生理不順を改善しているわけではないのですか?」という質問を受けることがあります。
ピルは、「飲んでいる間はホルモンバランスを整えて、定期的に出血を来させることができる」ものです。
ピルを飲んでいる間に、男性ホルモンが下がったり、LHとFSHのアンバランスさが改善したり、卵巣の「排卵しにくさ」が改善すれば、ピルをやめた後も月経は順調に来るようになります。
逆に、ピルを飲んでも、卵巣そのものの働きが改善しなかったり、「排卵しにくさ」が続いていると、ピルをやめた後に生理不順の状態に戻ってしまいます。
ピルを飲むことによって、その後の排卵が起きにくくなったり、不妊症になるという心配はありません。通常は、服用を中止したら、服用前より排卵しやすくなっているか、「服用前のまま」かのどちらかです。
ピルはいつまで飲まなければいけない?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
生理不順の治療目的でピルを飲む場合、できれば6クール(6シート)は継続した方がベターです。
ホルモンのアンバランスさを整えたり、将来的な子宮体癌のリスクを下げるには、6か月は継続して治療した方が効果的だからです。
10代の方が、ピルで生理不順の治療を行う場合は、6か月以上継続した後にさらに継続するのかいったん中止するのかを相談して決めます。受験や部活のスケジュール的に、生理がいつ来るのかがはっきり分かったり、生理の日を調節できた方が便利な期間中は、ピルを継続しておいた方がよいでしょう。
20~30代の方で、避妊も必要という場合は、6か月でピルをやめずにそのまま避妊もかねてピルを継続することをお勧めしています。
避妊が不要になった時や、妊娠を希望した段階でピルをやめた方が、トータルのメリットは大きいと言えます。
ピルで生理不順は治らない?(横浜 評判いい 婦人科 女医)
ピルで、ひとまず定期的に月経が来るようにしたり、足りないホルモンを補うことは重要です。
特に、多嚢胞性卵巣症候群で月経が不規則になっている場合、ピルで定期的に出血を来させておいた方が、将来的な子宮体癌のリスクを下げることにつながります。
ただ、ピルを飲むと同時に、「なぜ生理不順になったのか」を考えて、食事や生活習慣を見直したり、適切な体重にコントロールしたりすることも重要なのです。
ピルをやめた後にすぐに生理不順に戻ってしまう場合は、何を改善すれば自然な生理が定期的に来るようになるのかを、生理不順の原因から逆算して考えてみるとよいでしょう。
日付:2026年2月12日 カテゴリー:生理不順
生理不順の原因は?
生理不順の時にまず確認しておくことは?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
月経不順や無月経の原因は、かなり多岐に渡ります。
病気ではありませんが、「月経が来ない」という時にまず確認しておかなければいけないのは「妊娠していないかどうか」です。
不規則な月経がちょこちょこあって何だか変だな、と思って婦人科を受診したらすでに妊娠5ヶ月だったなんてケースもそんなに珍しくありません。全く性交渉をしていないという人以外は、月経が予定通りにきちんと来なかったらまず妊娠反応を調べてくださいね。
生理不順の原因で意外と多いのは多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)(横浜駅 評判いい 近くの 婦人科)
月経不順の原因として割とよくあるのが、卵巣機能の低下による女性ホルモン不足です。月経がきちんと来るためには、脳から卵巣へ「女性ホルモンを出しなさい」という命令が出て、その命令を受けた卵巣が卵を育てて女性ホルモンをきちんと出す必要があります。ところが、卵巣が疲れてしまったり、「多嚢胞性卵巣」のような体質的な異常で卵巣が上手く働けなくなると、この女性ホルモンが足りなくなってしまうんですね。ホルモンが充分に出ていないと、月経も正しく来なくなります。
卵巣が疲れてしまう原因としては、ストレスや冷え・不規則な食事・卵巣のう腫などの病気・加齢などが挙げられます。
また、卵巣は正しく働けるのだけれど、脳が卵巣に向かってきちんと命令を出していないために、結果として女性ホルモンが充分に出ていないという場合もあります。これを「視床下部性」とか「下垂体性」とか「中枢性」といったりしますが、ようは「脳」に原因があるということです。
卵巣に命令を出している「視床下部・下垂体」という場所はストレスに非常に弱い場所なんです。なので、強いストレスを感じたり、いきなり環境が変わったりすると、すぐにダメージを受けて充分な命令が出せなくなってしまうことがあるんですね。
脳が受けるダメージの中で一番大きいのは、実は「体重の減少」によるストレスです。つまり、ダイエットのし過ぎで急激に体重を落としたり、例えゆっくりでも大幅に体重を減らしてしまうと、脳はとても大きなストレスを感じで卵巣への命令をストップさせてしまいます。
こういった、ダイエットによる無月経を「体重減少性無月経」といいますが、ひどくなると無月経の中でも一番治療が難しく時間がかかってしまいます。
他にも、女性ホルモン以外のホルモンが脳の働きを邪魔して月経不順を引き起こすこともあります。「プロラクチン」というホルモンはお乳を作るホルモンなんですが、これがたくさん出過ぎるとちょうど授乳中と同じ状態になってしまい、排卵が止まります。胃薬や精神安定剤の中には、副作用の1つとしてこの「プロラクチン」を異常に高くしてしまうものがあるので、薬を飲み始めたら月経不順になったという人は、薬のせいではないか、医師に確認した方がいいですね。
また、甲状腺で作られる「甲状腺ホルモン」は出過ぎても足りなくなっても卵巣の働きを妨げてしまうことがあります。甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症が元々ある人は、きちんとホルモンがコントロールできているか確認した方がいいでしょう。
生理不順で受診したら何をされる?(横浜 婦人科 おすすめ 女医)
生理不順は気になるけれど、婦人科で何をされるのか不安でなかなか受診しにくい、という方もいらっしゃるかもしれませんね?
通常は、前述の原因を見分けるためには、まず血液検査で女性ホルモンや脳から出ている様々なホルモンの値を調べます。
また、超音波検査で子宮や卵巣そのものに異常が無いかどうかを確認します。
超音波の検査は、「腟から」「肛門から」「お腹の上から」の3つの検査方法があります。経腟的に見る方が細かいところまで見えるので、内診が可能な方は通常腟から検査をします。性行為の経験がない、または、内診に対する恐怖心が強い方の場合は、可能なら肛門から検査をします。10代前半の若い方や、下着をとること自体に抵抗を感じる方は、少し検査の精度が落ちますがお腹の上から超音波の機会を当てて検査をすることも可能です。
さらに、最近環境が変わったりしていないか、急激に体重が減っていないか、生活がハードになり過ぎていないかなどを詳しく伺うことによって、何が原因なのか見当をつけていきます。特に、ずっと順調だった生理が、急に乱れてきた時には、重大な病気が隠れていることもありますので、少しでも変だなと思ったら、早めに婦人科で検査を受けることをお勧めします。
日付:2026年2月12日 カテゴリー:婦人科の病気,生理不順
生理痛がひどくても病院に行かなくていい?【横浜駅近くの婦人科】
生理痛が「ひどい」かどうかの判断(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
正常な排卵周期の生理であれば、生理の時に全く不快な症状が出ないということの方が稀です。痛みの程度の差はありますが、多少下腹部や腰が痛くなったり、下半身が重だるくなることがほとんどです。
では、どの程度の症状だと、生理痛が「ひどい」といえるのでしょうか?
次のような症状がある場合は、生理痛を放置しない方がいいかもしれません。
*市販の痛み止めを1日3回以上飲まないとつらい
*市販の痛み止めがほとんど効かない
*腹痛や腰痛で立っていられなくなる
*生理痛のせいで学校や仕事を休む日がある
*痛みがひどいだけではなくて出血量も多い
*腹痛や腰痛以外に頭痛や吐き気を伴う
*生理の時に下痢になる
*下腹部痛だけではなく肛門痛や排便痛がある
生理痛が「ひどい」時の対処法(横浜市 評判いい 婦人科)
軽い生理痛や、生理の時期の体のだるさであれば、バランスのいい食事を心がけたり、体を温めたり、ストレッチや軽い運動で血行を良くすることで症状を和らげることが可能です。
市販の痛み止めも、上手に使えばある程度痛みをコントロールできますので、「ひどくない」生理痛ならセルフケアで上手に付き合っていくとよいでしょう。
ただし、最初に挙げたような「ひどい」症状がある場合は、自分で何とかできるものではありません。
「月経困難症」と言って、「病院で検査を受けて適切な治療をした方がいい」状態です。
特に、生理の量が多い「過多月経」を伴っていたり、肛門側の痛みや排便時の痛みも伴っている場合は要注意です。子宮筋腫や子宮内膜症などの、器質的な病気が隠れている可能性があります。
これらの病気の有無は、超音波検査を受ければわかります。婦人科を受診して、超音波検査を受けるようにしましょう。
性行為の経験がない場合は、超音波検査はお腹の上から又は肛門側から機械を当てます。膣からの診察をしなくても診断ができますので安心してください。
内診が不安で受診を躊躇している場合は、「内診はせずに検査をしてほしい」ことをあらかじめ伝えておくとよいでしょう。(性行為の経験がある方は、基本的に膣からの診察になります)
生理痛がひどい場合の治療法(横浜駅 おすすめ 近くの 婦人科)
痛み止めが効かないほどの生理痛の場合や、子宮内膜症を伴っている場合は、基本的にピルや黄体ホルモン剤による「ホルモン療法」が主流になります。
「ひどくない」生理痛であれば、体を温める効果のある漢方を使ったり、鎮痛剤を早めの時期から服用することである程度症状を和らげることが可能です。
鎮痛剤は、市販の痛み止めよりも効果が高いものが多く、作用の仕方が異なるものを組み合わせるとより効きやすくなります。痛みを我慢しきってから服用しても効果はいまいちになってしまいますので、鎮痛剤を使う場合は「痛くなってきたかも~」くらいのタイミングで躊躇せず飲むのがポイントです。
ひどい生理痛に対しては、低用量・超低用量ピル又は、黄体ホルモン剤(ディナゲスト)を使います。
ピルは、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの2種類のホルモンが混ざっている薬です。排卵を抑えて、子宮内膜を薄く保つという作用があります。この「子宮内膜を薄くする」作用が、出血量を減らして痛みを軽くしてくれるのです。
ピルは排卵を抑えますが、出血(生理)を来なくさせるわけではありません。定期的に出血は来るので、生理が来るタイミングをコントロールして、なおかつ生理を軽くしたいという方にはお勧めです。
最近は、連続服用タイプのピルも発売されていますので、生理が来る回数を3カ月や4カ月に1回にして、不快な症状に煩わされる機会そのものを減らすことも可能になってきました。
黄体ホルモン剤(ディナゲスト)は、黄体ホルモンだけが含まれた薬です。ピルとの大きな違いは、内膜をより薄く保つので出血がほとんど来なくなります。また、卵胞ホルモンが含まれていないため、吐き気や頭痛といった副作用がほとんどありません。
ピルほどは、血栓症リスクも上がらないため、例えば、片頭痛がひどくてピルが飲めない人や、年齢的にピルによる血栓症が心配な方にも使いやすい薬です。
いずれの薬も、婦人科で検査を受けて、どの薬が適しているかを相談して、処方してもらいます。
ひどい生理痛を放置すると、将来的な子宮内膜症や不妊症のリスクにつながってしまいます。また、毎月生理痛で寝込んでいては、やりたいことに力を注ぐこともむつかしくなってしまいますよね。
ぜひ、「痛くない快適な生理」にコントロールできるということを、体感してみてください。
日付:2026年2月11日 カテゴリー:生理痛
妊活に基礎体温は必須?
基礎体温で何が分かる?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医)
妊娠を希望している場合「まず基礎体温をつけましょう」と言われることも多いかもしれませんね。
基礎体温をつけると分かることは
*月経周期が正常範囲かどうか
*高温期と低温期があるか=排卵しているかどうか
*排卵の時期が月経周期の何日目くらいなのか
*高温期の体温が充分高いか
*高温期の継続日数が足りているか
などです。
なので、妊娠を考え始めたら、基礎体温はつけた方がよいと言えます。
ただ、生理周期が2~3日の誤差程度で安定しており、3周期くらい付けた基礎体温がきれいに2相性で高温期もしっかりある場合、「ずっと付け続けないと妊活できない」わけではありません。
基礎体温をつけなくてもタイミングはとれる?(横浜市 評判いい 婦人科 土曜日も)
周期が安定していて排卵していることが確実な場合は、生理の周期から逆算して妊娠しやすい時期が予測できるため、基礎体温をつけなくてもタイミングを合わせることが可能です。
「生理の周期ー14」が排卵の時期です。
排卵日の2~3日前からタイミングを持つと妊娠率が上がります。
例えば、生理周期が30日の人の場合、生理が来た日を「1日目」とカウントして「16日目」くらいが排卵日になるということです。
なので、「13日目~16日目」にタイミングを合わせるとよいと言えます。
逆に、生理の周期が5日以上のばらつきがある(例:35日の時もあれば42日の時もある)場合は、基礎体温を付けた方がタイミングは合わせやすくはなります。
ただ、基礎体温で『未来の排卵日の予測』は難しいので、周期の一番短い日に合わせてタイミングをとり始め、基礎体温が上がるまで1~2日おきにタイミングをとる必要があります。
生理不順だと妊活しにくい?(横浜市 おすすめ 婦人科 女医 土曜日も)
生理の周期がバラバラな場合は、基礎体温をつけていても排卵日の予測が難しい場合もあります。
尿検査で排卵日を予測する「排卵日検査薬」を使うと、「排卵直前」に陽性になるため、「今日がチャンス!」というのは把握しやすくなります。基礎体温と排卵日検査薬の組み合わせで、ある程度タイミングが合わせられるようなら、その状態で6クールくらい様子を見てもよいでしょう。
排卵日の予測方法として、一番確実なのは、超音波検査です。超音波で、卵巣の中にある卵の元(卵胞)を計測して、その大きさから「あと何日後くらいに排卵しそうか?」を予測します。
超音波検査は、不妊治療を行っていない婦人科でも対応できる検査です。
基礎体温だけではタイミングを予測しにくいという場合は、婦人科で相談してみるとよいでしょう。
生理不順の治療
生理不順は「薬」でないと治らない?(横浜 婦人科 女医 おすすめ)
無月経や月経不順の治療は基本的に「薬物治療」つまり薬によるものが中心になります。ただし、他のホルモンが悪さして二次的に月経不順になっている場合は、まず大元の病気を治療します。
例えば、月経不順の原因が、高プロラクチン血症だった場合はプロラクチンを抑える薬を飲んで治療します。高プロラクチン血症の原因が薬による副作用の場合は、その薬をまずやめますし、脳腫瘍の場合は腫瘍の手術を行うこともあります。
3ヶ月以上月経が全くない無月経の場合は、とにかくまず1度は出血を来させる必要があるので、ホルモン剤を1~2週間飲んだり筋肉注射でホルモンを補ったりして月経を起こすのが一般的です。
ただし、極端なダイエットによって月経が止まってしまった「体重減少性無月経」の場合は、出血がくること自体が体に大きな負担になってしまうので、例え3ヶ月以上月経が来ていなくても体重がある程度元に戻るまでは無理に月経をこさせないこともあります。体重減少性無月経の治療の基本は、まず体重を元に戻すこと。ある程度体重が戻れば、月経も自然に回復してくることがあります。
「ホルモン剤」は飲み続けなければダメ?(横浜駅 評判いい 近く 婦人科)
無月経の原因が一時的なストレスや環境の変化だったり、ホルモンバランスがまだ保たれている場合は、薬で1回月経を来させた後はしばらく基礎体温をつけるだけで様子を見てもいいでしょう。いったん出血を来させたら、その後はまた規則的に月経が来るようになることもあります。
逆に、元々月経不順だった人がとうとう全く月経が来なくなったというパターンや、血液検査で女性ホルモンが極端に少なくなっている場合は、少なくとも3ヶ月間は薬を続けてその後もきちんと月1回の出血が来るようにした方がいいでしょう。
月に1回のペースで定期的に出血を起こすことにはとても大事な意味があります。月経は子宮のお部屋の中で厚くなっていった「子宮内膜」が月に1回はがれて体の外に出てくる現象です。つまり毎月子宮の中を大掃除しているようなものです。
月経不順や無月経で、この子宮の大掃除が定期的にできなくなると、子宮の中では古くなった「子宮内膜」がたまってしまうことがあります。そうすると、子宮内膜に変化が起きやすくなって「子宮体癌」のリスクになってしまいます。
ホルモン療法の基本は「ピル」(女医だけ 婦人科 横浜)
薬で月経を起こす方法は、低用量ピルや超低用量ピルを使うことが増えてきました。ピルは1錠の中に必要な女性ホルモン2種類が含まれている合成のホルモン剤です。確実な避妊にもなりますし、飲み方も簡単で月経も楽になるので、生理不順だけではなく生理痛やPMSが気になっている場合にも活用できます。
他にも、2種類のホルモン剤を組み合わせてホルモンを補う「カウフマン療法」という方法があります。いずれにしても、本来卵巣から出るべき女性ホルモンを飲み薬で体の外から補うことによって、月経と同じ出血を起こすわけです。
月経不順で無排卵になっていても、すぐの妊娠を希望していなければ基本的には排卵誘発剤は使いません。卵巣が疲れているから月経不順になっているのに、その卵巣に鞭打って無理やり排卵させるのは卵巣にとってはかなりの負担になってしまいます。
ただ、妊娠を目指してる方の場合は、何とかして排卵するようにしなければ妊娠は望めませんから、初めから排卵誘発剤を使ってとにかくきちんと排卵するように治療を進めていきます。
月経は不規則だけれど60日以上は間があかないとか、ホルモンが少なめだけどある程度保たれているという場合は、ホルモン剤を使うのではなく、体を温めたり血液の流れをよくする漢方薬を飲んで様子を見ることもあります。
漢方薬を飲むだけでなく、生活習慣の改善も一緒にしていくことで、卵巣の働きが戻りやすくなります。生活改善のポイントは、適切な体重を保つ・バランスの良い食事をとる・適度な運動をコンスタントにする・湯船に毎晩30分以上ゆったりつかる(シャワーで済ませない)・ストレスをためない・禁煙する、などです。
月経不順は体からのSOSですから、無視せず今の生活を見直すきっかけにしてみてください。
日付:2026年1月27日 カテゴリー:婦人科の病気,生理不順