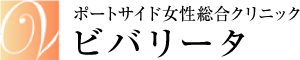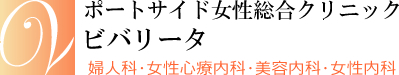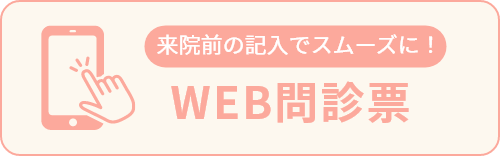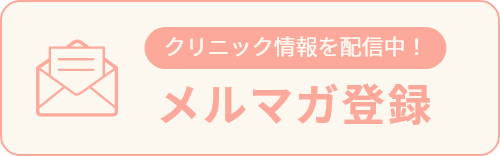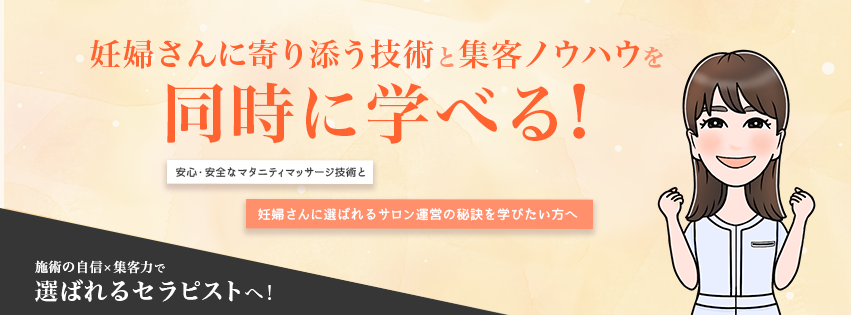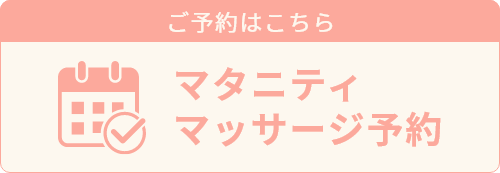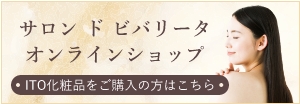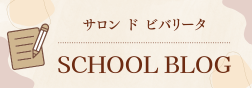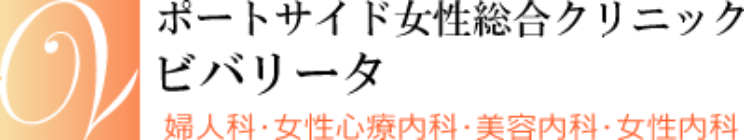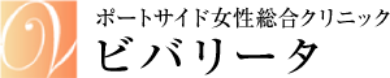女性検診
子宮頸がん検診の間隔は?
自治体が行っている子宮頸がん検診の助成対象は「20歳以上」「2年に1回」となっているところが多いのですが、実際はどのくらいの間隔で子宮がん検診を受けたらいいのでしょうか?
HPVの感染から子宮頸がんになるまでに少なくとも3年かかると言われています。
なので、本当は20歳になっていなくても性交渉開始から3年たっていれば子宮頸がんになる可能性はあるので、性交経験があれば10代でも検診は必要です。
検診の間隔は、前回の検診が「異常なし」という結果でその結果が100%正しければ理論上は3年に1回でいいということになります。ただ、検査には必ず一定の確率で「偽陰性」つまり不正確な結果が出る事があるため、3年は明けずに受けましょう、という意味で2年に1回となっています。
ただ、現在の検診方法である細胞診のみの検査だと、2年あけるのはリスキーであるという意見もあります。より確実に子宮頸がんを早期発見しようと思ったら、やはり1年に1回の検診を受けるのが理想的といえるでしょう。
「検診間隔を3年に1回にしても大丈夫」と言えるのは、細胞診とHPVハイリスクタイプ検査の両方が「異常なし」という結果だった場合です。
この場合、現時点で癌の手前の「異形成」という病変以上の変化はほぼ100%ありませんよと言えますから、次の検診は3年後で大丈夫なわけです。
検診で行うHPV検査は自費になりますが、毎年子宮頸がん検診を受けるのはちょっと大変だな、という方は併用検診を受けてみてはいかがでしょうか。
日付:2010年11月8日 カテゴリー:女性検診,子宮頸がん検診
婦人科検診の内容は?
一口に「婦人科検診」と言ってもその内容は受ける検診や病院によって結構異なっていたりします。
会社で受ける健康診断や人間ドッグにオプションでついている「婦人科検診」は、多くが子宮頚がんの検査と内診(触診)のみなんですね。実は、これだけでは子宮筋腫や卵巣のう腫や卵巣がんのチェックは充分できません。
婦人科検診として、最低限受けておくべき検査は「子宮頚がん検診」と「経膣超音波検査」です。超音波の検査を加えることによって、子宮や卵巣に形・大きさの異常がないか確認できます。
また、年齢が40歳以上の方は子宮体がんの検査も加えておくと安心です。
会社によっては、子宮頚がんの検査を「自己検査」で行っているところもあるようですが、これは見落としのリスクが高いのでおすすめできません。
子宮頚がんの検査は、正しい場所から正しい方法で充分な細胞を擦り取ってこなければ正確な検査ができないんです。自己検診だと、正しい位置から細胞を取ったかどうか確認できませんよね?
子宮頚がんの検査は、必ず医師による検査を受けるようにしましょう。
これ以外にも、年齢別の受けておいた方がいい検査があります。
10代~20代で性交経験がある方は、この年代が最も性感染症にかかっている率が高いので、クラミジアや淋菌感染などのいわゆる「性病チェック」をしておいた方が安心です。
30代の方は、子宮頚がんのリスクが高くなってくる年代なので、子宮頚がん検査と一緒にHPVハイリスクタイプの感染がないかをチェックしておくといいでしょう。
40~50歳の方は、ホルモンのアンバランスがおきやすくなりますので、特に更年期や月経不順が気になる方はホルモンチェックを受けておくことをお勧めします。
自分がどの検診を受けた方がいいのか分からない、という方はご予約の際にご案内いたしますので、お気軽にご相談くださいね。
日付:2010年10月12日 カテゴリー:女性検診,日々の雑記
HPVワクチンとは
HPVはヒトパピローマウイルスの略で、約100種類の「型」に分類されています。このうち、子宮頸がんの組織から見つかっている「型」がいくつかあり、それらを「ハイリスクタイプ」と言って他の型とは分けて扱っているんですね。主なハイリスクタイプは、16型・18型・31型・45型・52型・58型などです。
昨年末に発売されたHPVワクチン(サーバリックス)は、これらのハイリスクタイプHPVのうち、16型と18型の2種類のみを予防するワクチンです。きちんと接種すれば少なくとも7年はほぼ100%の予防効果が期待できることが確認されています。これは、7年しか予防効果がないということではなくて、確実に予防できていると追跡調査できた期間が7年までという意味で、実際はほぼ一生予防効果は持続すると予測されています。
16型と18型が原因となっているケースが最も多く、子宮頸がんの約6割はこの2つのどちらかが関わっています。つまり、ワクチンによってこの2種類がブロックできれば、子宮頸がんのリスクを6割減らせるということです。ただし、ワクチンを打っても残りの4割はブロックできませんから、子宮頸がんになるリスクが「ゼロ」になるわけではありません。ワクチンを接種しても子宮がん検診は必ず受けるようにしてくださいね。
ワクチンが最も有効なのは、HPVに感染する前つまり性交渉を始める前です。なので、10代の性交経験前の女性が最優先対象となります。病院でも、「私はもう打っても意味がないかもしれないけれど、娘に打っておきたいので」とパンフレットを持っていかれる患者さんも結構いらっしゃいます。
性交経験後であってもHPVの16型や18型に感染していなければワクチンの意味は十分にありますし、20代や30代でも効果が期待できないわけではありません。ただ、性交開始からの年数が長ければ長いほど、HPVに感染している可能性は高くなりますから、年齢とともに効果が下がってしまうということなんですね。
接種前のHPV検査は不要となっていますが、どうしても気になるようであればHPVに感染しているかどうかを事前に確認するための検査は可能です。ただしこの検査は保険がききませんので、自費になってしまうんですね。個人的には、子宮がん検診で異常が出ていないのであれば、HPV検査はしなくてもいいのではないかと思います。
ワクチンの値段は、大体1回18000円~20000円くらいになります。全部で3回の接種が必要なので、3回分まとめて50000円くらいにしている病院もありますね。ワクチンも自費ですので病院によって値段が異なります。料金については事前に確認しておくといいかもしれません。
日付:2010年5月20日 カテゴリー:HPVワクチン,女性検診
HPVワクチン最新情報
3医会合同講習会で仕入れてきた、HPVワクチンについての最新情報をお伝えしますね。
女子大生におけるHPV感染の追跡研究では1年以内で約15%・3年以内で約45%が陽性化するそうです。それらをさらに追跡すると、陰性化する頻度が6ヶ月で30%・12ヶ月で70%・24ヶ月で90%。つまり、過半数の女性が一生に一度は感染するけれど、2年以内に9割の人はHPVの検査が「陰性」になるってことです。
全女性の50~80%が感染するわけですから、演者の先生はHPV感染は子宮が風邪をひいたようなものだとおっしゃっていました。
一方で、若い頃からこのHPVに感染してしまう事は、20代30代で子宮頸がんが増えている事と明らかに関係しています。
HPVの検査をすると陽性率は15~19歳がピークで4割以上の人が陽性で出ます。年齢とともに徐々に陽性率は下がっていって、35~39歳以降で10%以下になるんです。
ただ、「検査で陰性になった」ことがイコールHPVが排除されたという事にはならないんだそうです。HPVは排除されるわけではなく、検査で引っかからない状態で潜伏し続けるらしいんですね。
だから、一度でもHPVにかかってしまったら、例え検査で陰性化しても子宮頸がんになるリスクが下がったと安心してはいけないとおっしゃってました。
この潜伏の状態だとウイルスも悪さはしませんので、子宮頸がんに細胞の変化が進んでいく事もありません。いつ潜伏状態からウイルスが目覚めるかが問題なだけなので、1年に1回の検診を受けていれば心配する必要はないんですね。
ただ、ウイルスがすでに潜伏しているという事は、感染後にワクチンを打っても効果が得られないかもしれないという事です。こういった、検査では「陰性」となってしまう潜伏感染は当然年齢とともに多くなっていきますから、ワクチンの効果も年齢とともに下がってしまいます。
30代や40代の方がワクチンを打っても害はありませんが、予防効果という意味でもあまり効果は期待できないとのことでした。
なので、30歳以上の方がワクチンを打ちたいとおっしゃったら、もしかしたら効果がないかもしれないことと必ず年に1回の子宮頸がん検診は必須である事をご理解いただいた上で接種することになるんですね。
ちなみに、最優先接種対象者は、性交経験がない女性です。
何歳であっても、性交経験がなければHPVに感染していないわけですから、ワクチンによって70%もの予防効果を期待できます。
海外では、10~12歳くらいで公費負担で接種している国が多くて、それ以降の年齢でも25歳くらいまでは優先的に接種する対象になっています。
また、子宮がん検診で軽い異常が出ていても、ハイリスクタイプのHPVに感染していても、コンジローマにかかった事があっても、10~20代であれば50%の予防効果は期待できるので、HPVの16型や18型に感染しているかどうかの検査はせずに、優先的に接種する事を勧めた方がよいとのことでした。
患者さんにもよく聞かれるのですが、「コンジローマにかかった事があったらワクチン打てないんですか?」とか「HPVの検査で陽性が出てしまったらワクチン打っても意味がないんですか?」という心配は必要ないという事です。
逆に、ワクチンによる予防効果があまり期待できないケースは、明らかに16型や18型に感染していることが分かっている人・すでに円錐切除を受けた人・40歳以上の人です。
同じ手術後でも、レーザー蒸散によって治療した後の人は、再発予防のためにワクチンは接種した方がいいとのことでした。
30歳以上の人については、ワクチンを打つよりも定期的な子宮がん検診をサボらない事の方が重要になってくるのですが、海外と比べて検診の受診率が約20%という低さの日本では、30代や40代でもワクチンを打った方がいいのではないかという考えもあるそうです。
いずれにしても自費なので、接種するかどうかは本人の希望次第なんですが、接種前のHPV検査は不要とはっきりおっしゃっていただけたので、ワクチン接種代以外はそれほどかからずすみそうですね。
1度HPVにかかったからワクチンは無理だわ~とか、レーザー蒸散した後だから意味がないかも、とあきらめていた方も、ワクチンの効果が期待できそうなので、担当の医師に相談してみるといいかもしれませんね。
日付:2010年5月20日 カテゴリー:HPVワクチン,女性検診
子宮がん検診を受けましょう
1)日本の検診受診率の低さ
婦人科の検診を受けた事のある人は、案外少ないのではないでしょうか。30歳(居住地域によっては20歳)を過ぎると、がん検診受診を促すハガキが送られてきた人もいるはず。せっかく無料叉は格安で定期検診が受けられるチャンスなので、上手に利用してみて下さいね。
厚生労働省が発表している「がん検診の受診率の推移」によると、子宮がん検診の受診率は若干減少傾向で約15%。ちなみにアメリカの女性の子宮がん検診受診率を見てみると、1988年の時点で3年に1度でも検診を受けた事のある女性が79%です。日本の女性も、もっと「自分の健康は自分で守るもの」という意識を持って欲しいなと思います。
2)子宮癌検診は意味がある?
子宮がんの罹患率(かかる人の割合)は、確かにわずかに減少傾向です。でも、20代や30代での早期の子宮がんの発見は逆に増えてきているんです。
子宮癌は早期(0期叉は1a期)に発見されれば、子宮の一部叉は子宮全部をとることでほぼ完全に治療する事が可能です。しかし、早期の場合自覚症状はほとんど出ません。不正出血や接触出血(性交後の出血)といったはっきりとした自覚症状があったときには、たいてい進行癌の状態になってしまっているんです。
治療可能な早期のうちに癌を発見するためには、定期的に検診を受ける以外に方法はありません。
検診の種類にも色々あって、発見率の低さからあまり有用ではないとされるものも中にはあります。
でも子宮頸がんの検査は違います!厚生労働省の「がん検診の適正化に関する研究班報告」でも、「検診による死亡率減少効果があるとする十分な根拠がある」ものの一つとして「細胞診による子宮がん検診」を挙げています。ちなみに、このランクの検診は他に「視触診とマンモグラフィの併用による乳がん検診」と「便潜血検査による大腸がん検診」です。
3)なぜ20代でも必要?
20代で癌の心配をする人は、非常に稀だと思います。でも、30代で発見される子宮癌が増えているということは、その癌の「芽」は20代のうちに出てきているという事なんです。
癌はいきなり癌になる訳ではありません。細胞が徐々に変化して、顔つきを変えていって、そして癌になっていきます。稀に、正常な細胞からいきなり癌になってしまうタイプのものもありますが、少なくとも子宮頸がんによくあるタイプの癌は徐々に変化していくタイプのものです。
この変化には何年という時間がかかります。なので、その途中で発見する事が出来れば、早いうちに癌の芽を摘み取ることが出来るというわけです。
じゃあ何歳くらいから調べるのが適切なのか・・・・性交経験の開始から3年以内、もしくは20歳を過ぎたら、2年に1回は検診を受けるべきです。
この根拠の一つは、先ほど書いた癌の発生時期の問題。もう一つは、子宮頸癌の原因の一つとして注目されてきている、HPVというウイルスの感染と関係しています。
HPVは性交でうつる性感染症の一種ですが、このウイルスのあるタイプに感染すると、子宮頚部の細胞の変化がおこりやすく、将来的に癌になりやすくなってしまうんです。ウイルスに感染してから約3年で細胞の変化が起こってくると言われています。なので、例え10代でも性交開始から3年経っていれば検査を受けておいたほうがいいという事になります。
4)検診の間隔は?
厚生労働省は子宮頸癌の検診開始年齢を30歳から20歳に引き下げる代わりに、1年に1回としていた受診間隔を2年に1回にしていく方針を打ち出しました。
実際どのくらいの間隔で受診したらいいのかというと・・・・年単位というペースで細胞が変化していく事を考えたら、前回の結果が「異常なし」であれば2年間隔でも問題ないと考えられます。しかし、偶発的におこってくる見落としが約5%あることを考慮すると、1年に1回受けていれば安心といえるでしょう。
もちろん、結果が「グレーゾーン」であれば、検査の間隔は2~3か月になりますし、術後の再発チェックの方の場合も受診間隔は短くなります。
乳がん検診を受けましょう
食生活の欧米化に伴って、日本女性にも乳癌が増えつつあります。現代では25人から30人に1人は、生涯の間で乳癌にかかる可能性があるというくらい。女性の癌死亡原因では、乳癌がトップになってしまいました。
とはいえ、まだまだ他人事、という意識の方が多いのか、乳癌検診の受診率も10%ちょっとという低さ・・・・しかも、まだ多くの方が乳癌検診は婦人科で受けるものだと誤解されているようです。
乳癌は「乳腺外科」の医師が診ます。乳癌検診は乳腺専門の外科で受けるものなんです。
乳がん検診が必要になってくるのは、30歳以降。自治体の検診では40歳以上が検診の対象になっていることが多いんですが、30代で乳癌になるケースは少なくないんですよ。早期発見のためには、30歳を過ぎたら年に1回マンモグラフィー+超音波検査の併用できちんとした検診を受けてくださいね。
卵巣がん検診を受けましょう
1)沈黙の臓器と言われるわけ
卵巣は別名「沈黙の臓器」と言われています。少々腫れていても、まったく症状が出ないことが多いからなんですね。
例えそれが悪性、すなわち癌であっても、かなり進行してあちこちに転移したりお腹の中に水がたまったりして、やっと発見される事も稀ではありません。そのため、卵巣癌は「サイレントキャンサー」とか「サイレントキラー」と呼ばれているくらいなんです。
正常な卵巣は、親指の先くらいの小さな臓器です。だから、これが少々腫れても、お腹の中では大して圧迫感も無ければ痛みも出にくいんですね。
良性の場合でも、卵巣の腫れが5cmを超えると、卵巣がくるっとねじれてしまう「茎捻転」という状態になる事があります。この時だけは、お腹に激痛が生じますので、緊急で病院に運ばれて手術になる事もあります。
2)卵巣癌は増えている
卵巣癌が癌全体の中で占める割合としては3.2%と多くはありませんが、発症率は増えてきています。卵巣癌による死亡率は、1950年には人口10万人対0.8だったのに、約40年後には5.4まで上昇しているんですね。
これには、食生活の欧米化(コレステロールの摂取量の増加)や喫煙率の増加、妊娠・出産の回数の減少などが原因と考えられています。
3)卵巣嚢腫は若い人に多い
卵巣嚢腫は、卵巣の良性腫瘍の総称です。つまり、卵巣は腫れているけれど癌ではないものをまとめてそう呼んでいるんです。
卵巣癌になりやすい年齢は閉経前後、つまり40~50歳代ですが、卵巣嚢腫は逆に20~30歳代の若い女性に多く見られます。
卵巣の組織はとても複雑で、卵巣嚢腫の元になっている細胞が何かによって何種類もの分類があります。代表的なものは「成熟奇形腫(皮様のう腫)」や「チョコレートのう腫」です。
4)どうすれば発見できる?
卵巣の腫れを発見する方法は、腟からの超音波検査やCT・MRIなどの画像検査です。ある程度の大きさになれば、触診、つまり触っただけでも分かりますが、ほとんど正常と変わらない程度の腫れですと、触るだけではわかりにくい場合もあります。
ただし、検診で年1回CTやMRIをとるというのは、かなり非効率的ですし、医療費の無駄使いになってしまいます。子宮癌検診を受ける際に、一緒に腟からの超音波検査をすれば、卵巣の腫れもチェックできますし、子宮筋腫や子宮内膜症がないかどうか、子宮内膜が分厚くなりすぎていないかなどの確認も一緒にする事が出来ますよ。
超音波検査は自費になってしまいますが、どうせ検診を受けるなら、ぜひ一緒に受けておくことをおすすめします。
子宮がん検診の結果の見方
検診の結果は郵送で受け取ったり、病院の窓口で報告書だけ渡される事も多いと思います。まったく問題なければまあ、特に心配せずにすむでしょうけれど、「クラス2 半年後に再検査を受けてください」なんて書かれていると、「え?癌なの?癌じゃないの?」「何で再検査がいるの?」なんてパニックになることも・・・・
検査結果の大まかな見方は、知っておいた方がいいでしょう。
子宮頸癌の結果は、クラスの1~5に分けられています。簡単に分けると、クラス1~2が「白=癌ではない」、クラス3が「グレー=癌になりかけの疑いがある」、クラス4~5が「黒=癌」ということになります。
クラス3はさらに3つに分かれていて、白に近いグレーなのか黒に近いグレーなのかによって、その後の治療方針が変わってきます。
以下に、大体のクラス分けの意味を書いておきます。これはあくまで目安の解釈なので、特にクラス3以上の結果に関しては、その後の検査や治療の方針はケースバイケースになります。
クラス1⇒まったく異常ありません。正常な細胞のみです。
クラス2⇒炎症による変化や加齢による変化など、癌とは関係ない良性の変化が見られます。
クラス3a⇒やや細胞の顔つきに変化が見られます。白に近いグレーです。7~9割は自然にクラス1~2に戻りますが、残りは変化が進んでいく可能性があるので、2~3か月後の再検査や精密検査が必要になります。
クラス3⇒中等度の細胞の変化がみられます。組織診による精密検査をして疑わしい場合は「円錐切除=子宮の一部を切り取る手術」による診断が必要になる事もあります。
クラス3b⇒かなり強い細胞の変化が見られます。「円錐切除」による診断及び治療が必要になります。
クラス4⇒上皮内癌が疑われます。「円錐切除」叉は子宮をとる手術が必要になります。
クラス5⇒浸潤癌が疑われます。転移の有無を調べたり、手術や抗癌剤や放射線による治療が必要になります。
子宮がん検診の受け方
子宮頸がん検診は、基本的に婦人科であればどこでも受けられます。
「検診希望」と言って受診すると保険がきかず、何らかの症状があって受診すると保険で検査してもらえます。自費で受けても数千円の検査ですから、それほど高いものではありません。
市や区から「癌検診を受けましょう」というハガキが届いた方もいらっしゃるでしょう。これは、「老人保健事業」の一環として20歳以上の人は隔年で子宮頸がん検診が受けられるように国が補助を出しているんです。なので、ハガキで指定されている医療機関で指定時期に検診を受けると、無料もしくは格安で癌検診を受けることができます。
癌検診を受けたいな、と思ったら、まずは近所の婦人科クリニックなどに電話で問い合わせてみるといいでしょう。最近は完全予約制のクリニックも増えてきていますから、事前に予約しておいた方がスムーズです。
また、病院によってはランチタイム検診など、忙しいOLさんでも仕事の合間に検診が受けられるように時間設定してあるところもあるので、ネットで色々検索してみることをお勧めします。
検診のみの場合、保険証は無くても受診できますが、ついでに何か治療をしてもらったり、他の検査をする可能性もあるので保険証は持って行っておいた方がいいですね。
がん検診のみだと、あまり詳しい問診票を書く必要は無いのですが、記入する用紙は病院によって色々なので、渡されたものに必要事項を記入していきます。
診察は、内診台にあがって行います。
内診台にあがると、まずは指で子宮の大きさなどをみる「触診」をします。
次に、「クスコ」という腟内を広げてみる器具を入れて子宮の出口を観察します。
この時見える子宮の出口=子宮頸部が、がん検診をする場所なんですね。
子宮頚部を綿棒やブラシのようなものでちょこちょこっとこすって細胞を取ったら終了です。頸部は少々こすっても、少し違和感を感じる程度で痛みはほとんどありません。
これらの検査は、一通り普通にすればほんの1~2分で終わります。
患者さんの中には「え?もう終わったんですか?」なんておっしゃる方もいるくらい、本当にあっという間に終わるんですよ。
場合によっては、超音波の検査を追加することもありますが、それでもトータルで5分もかかりません。
内診の時に痛い思いをしてしまうのは、たいてい使う「クスコ」のサイズが合っていなくて、大きすぎる場合ですね。クスコには、SSSからLまで各サイズがあるんです。
初めて婦人科の診察を受ける方や、お産の経験がない方、高齢の方などは、SSクスコでないと痛みを伴ってしまうことがあります。逆に、性交経験があればSSやSのクスコは普通に入るはずなんです。
以前痛い思いをしてしまったとか、初めての検診で不安という方は、内診の時に「小さめのクスコを使ってください」とリクエストしておくといいですよ。
検査結果は1~2週間で出るのですが、結果が郵送で送られてくる場合、受診から1ヵ月後くらいに届くこともあります。
結果の確認方法は、「病院に行って結果を説明してもらう」「郵送で報告書が届く」のいずれかがほとんどです。中には電話で結果を教えてくれる病院もありますが、個人情報保護の問題があるので最近では電話で患者情報は言わない流れになってきています。
受診してしまえば、おそらく「あ、こんなもんか」と思うほどたいしたことのない検査なんですが、それでもなかなか受けていただけないんですよね。
ちなみに私は、1年に1回の検診を忘れないようにお誕生月に受けるようにしています。
誕生日が来ると「あ、そろそろ検診受けなきゃ」って思い出せるので便利ですよ。
1年のうちたった5分我慢するだけで子宮癌のリスクから逃れられるわけですから、「めんどくさい」なんて言わないでしっかりセルフメンテナンスして欲しいなと思います。
子宮頸がん検診の受診率
女性の癌発症率を見ると、20代では圧倒的に子宮頸癌が多くて、30代でもトップは子宮頸癌。30代になると乳癌が増えてはきますが、それでも子宮頸癌の半分くらいです。にもかかわらず、乳癌検診はピンクリボンキャンペーンなどでかなり大々的にアピールされていますが、子宮頸癌検診に関する情報はまだあまり広まっていません。
セックスの経験があれば、10代であっても1年に1回は子宮頸癌検診が必要であるということも、定期検診によって早期発見できれば子宮を残したままでほぼ100%の完治が期待できることも、ワクチンとコンドームによって予防できる癌であることも、ほとんど何も知らない人のほうが多いんですよね。
これが、日本女性の癌検診受診率が低い原因のひとつであることは確かです。若い人ほど検診を受けておらず、また妊娠・出産する年齢も上がってきているので婦人科に行く機会もありません。
「知らなかった」では済まされないことですが、実際はまだまだ必要な情報は伝わってないんですよね。
イギリスでは、25~64歳の女性が3年に1回(50歳以上は5年に1回)、全額公費で子宮頸癌の検診を受けられるようになっているそうです。そして、検診受診率は約80%・・・日本の15%とは大きく異なります。
また、HPV検査を併用することで、より検診の精度を上げているそうです。HPVワクチンは12~13歳で国の公費負担で実施されており、12~13歳で接種できなかった人も18歳までに再度受ける機会が設けられています。
ちなみに、HPVワクチンは世界105カ国で承認されており、先進国の中で承認されていないのは日本と北朝鮮と中国くらいでした。それが、昨年やっと承認されて、年末から接種が可能になりました。
オーストラリア・ノルウェー・ドイツなどでは、12~13歳の女性に国が全額公費で接種しています。ちょうど、昔の風疹の予防接種のような感じです。アメリカ・イギリス・フランスといった国々でも、大体11~14歳で接種するようになっています。
オーストラリアやニュージーランドやオランダでは、男性へのHPVワクチン接種も認められています。ワクチンそのものが非常に高いので、子宮頸癌になる側、つまり女性が優先的に接種の対象にはなるんですが、本当は女性にHPVを感染させるのは男性なわけですから、男女ともに予防接種した方がいいんですよね。
日本では、まだHPVワクチンを公費負担で行っている自治体はわずかで、接種にかかる費用約5万円は自己負担になります。本当は、中学入学時くらいに学校で集団接種した方が予防効果が期待できます。
HPVは性感染症なわけですから、性行動が始まる前に、女性全員に取りこぼしなく接種できることが大事なんです。
イギリスでは、中学生や高校生の頃からきちんと子宮頸がん予防や避妊に関する教育を受け、テレビのコマーシャルなどでも啓発されており、大学生になったら検診を受けるようにハガキが来るんだそうです。
10代の頃から「セックスの経験があれば子宮頸癌になる危険性がある。年に1回は子宮癌検診を受けること」ということをしっかりと刷り込まれているので、検診を受けるのが当たり前という意識が大人になる前に育っているんですね。
この辺りが、日本と海外の検診受診率の違いを生んでいるのではないでしょうか。日本では、ティーンを指導すべき立場の親や教師だって、子宮癌検診も乳癌検診も受けていなかったりしますからね。
病院は病気になった時に駆け込むもの、という認識を持っている人が多いのは、国がそういった教育をしてしまい、国民皆保険制度によって、「病気になっても安く治してもらえるんだから」というある意味健康意識の低い状態を育ててしまったからではないかと感じています。
これから日本の若い女性が子宮頸癌で子宮を失っていかないようにするためには、やはり検診の必要性を伝えていくしかないのですよね。私も、高校生に性教育に行くたびに「10代でも子宮頸癌検診が必要なんですよ」ということを呼びかけていっています。
検診を受けない最大の理由は「めんどくさい」なんだそうです。
自分だけは癌にならない、と思っている人に癌検診を受けてもらうための1つの動機付けとして、HPV検査は有効かもしれないなと思いました。癌になるかもしれないウイルスに感染していると分かれば、少しは真剣に検診を受けようって思ってはもらえないかしら。