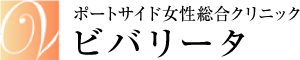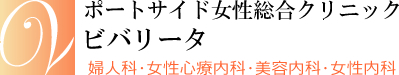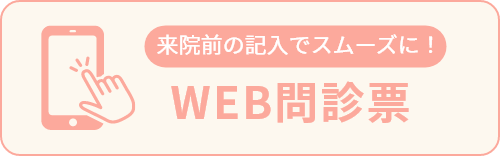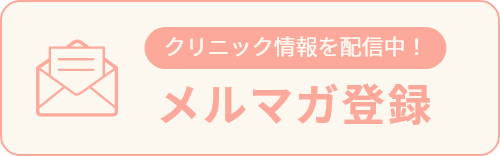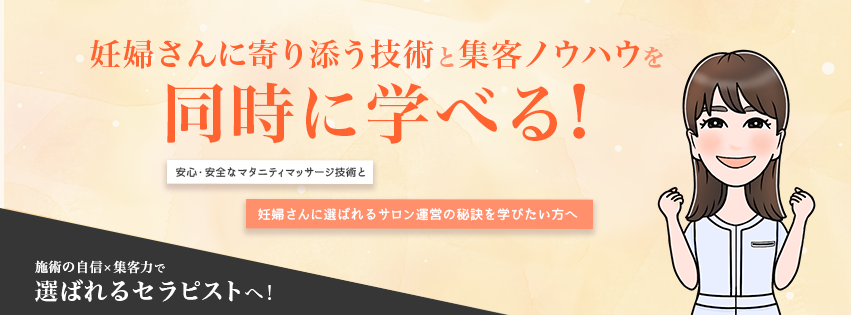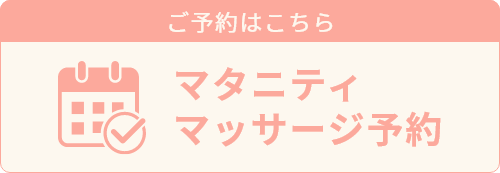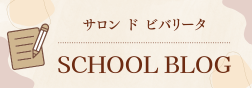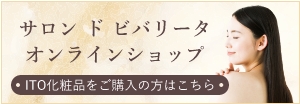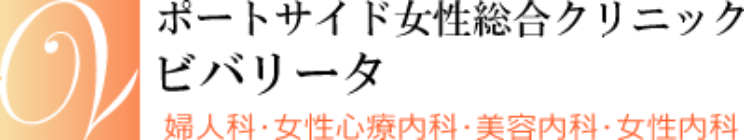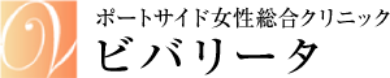日々の雑記
あなたは「超高性能アラーム」を活用していますか?
患者様とお話ししていると、「疲れると頭痛が出ます」「ストレスがかかると生理不順になるんです」「寝不足になると血圧が上がります」など、「こういう状況になるとこういう体調不良が出る」というパターンを認識している方も結構いらっしゃいます。
そんな時は、私はこう思うのです。「おめでとうございます!あなたは他の人にはない『超高性能なアラーム』をお持ちなんですね」と。心身に負荷がかかった時、それが命にかかわるような状態になる前にちゃんとわかりやすい症状としてサインが出てくれるわけですから、これほどありがたいアラームはありません。
でも、多くの方はこのアラームを「疎ましいもの」と捉えて、何とかしてアラームが鳴ること自体を止めようとします。
更年期症状が強く出る方には、「女性ホルモンはガソリンと同じです。更年期とい時期は、今後ガソリンが継ぎ足されない状態で約30年間の人生を過ごしていくために、体との付き合い方を探る時期です。これまでフルアクセルで走ってきていて、自分でブレーキを踏むことができない人ほど更年期の症状は出やすくなります。フルアクセルのままだとすぐにガス欠になってしまうからです。更年期症状は、体が『走り方を変えてくださいよ』と優しくブレーキを踏んでくれているから出るんですよ」とご説明しています。
中には、この話をしただけで涙を流される方もいらっしゃいます。どれだけ自分の体に鞭打ってきたか気づいたり、「誰かにストップと言ってほしい」状態を指摘されて安心されたりするのでしょう。
例えば、「疲れると頭痛が出る」人が、頭痛が出るたびに「もうまた頭痛!勘弁してよ」と思いながら鎮痛剤で頭痛を抑え込んで何とかしようとすると、頭痛が出るたびに脳の「苦痛系」という部位が刺激されます。これは、そもそも頭痛が起きることを「嫌なこと・避けたいこと」としてとらえているからです。この状態では、アラームがアラームとして機能していません。なので、これを続けているともっと重大な病気につながっていきます。
逆に、頭痛が起きたときに「あ、また頭痛だ。そういえば最近仕事を抱え込みすぎているな」と、それが「何のサインなのか」を読み取って好ましい状況になるように調整すると、頭痛が起きても脳の「報酬系」という部位が刺激されます。頭痛を「嫌なこと」ではなく「理想の自分からずれた時に元に戻れるようにしてくれるサイン」としてとらえているので、頭痛が起きるたびに「理想の自分に戻ろうとする」という力が働きます。なので、たとえ頭痛が「治っていない」状態でも、重大な病気に発展していかないのです。
何らかの体調不良が出やすい人は、それだけアラーム機能の感度がよいということです。
せっかく備わっている「超高性能アラーム」を、あなたは活用できていますか?
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
産後うつや虐待を予防する効果的な支援とは
今日も朝から学会参加です。朝イチのシンポジウムは、どのようにしてサポートが必要な妊婦さんをピックアップして、効果的な支援を行っていくかというテーマでした。母子手帳や問診票、質問紙票をうまく活用して、リスクをスコア化する取り組みや、産後健診などの行政的取り組みなどについて、各立場からのお話があり、色々参考になりました。
リスクというのは、虐待のリスクです。虐待死の6割以上が0歳の時点で起きているため、産後の母親をどのように支援するかが、虐待死を減らすためにはカギになるというわけです。今回は、産後うつのリスクについては議論の対象になっていませんでしたが、基本的な考え方は同じでしょう。
産後に継続的なサポートが必要になりそうな妊婦さんを、妊娠中から見つけておくことは、産後1ヶ月健診後も誰がどのように介入するのか、あらかじめ対策を立てる上では重要です。
でも、シンポジウム全体を通して強く感じたのは、事前にハイリスクとわかるケースばかりではないという点と、どんなに病院や行政が頑張っても24時間365日サポートすることはできないということです。例え区役所に育児相談に行っても、その時は話を聞いてもらえて少しは気分が晴れても、自宅に帰ればウンザリする現実があるわけです。妊婦さん本人だけを見ていても、十分なサポートにはならないのではないかと感じました。
じゃあどうすればいいのか・・・妊婦さんのごくごく身近にいる支援者を支援&教育することが重要なのです。支援者の一番の候補は、妊婦さんの「夫」です。子どもの「父親」という立場にいる人です。
両親学級への参加を必須にするとか、妊婦健診に4回以上同席させるとか、分娩時の立ち会いを勧めるとか、退院前の指導を母親だけでなくて父親も一緒に行うとか、父親をなんちゃってイクメンではなく「父親」として機能できるようにするために行えることはたくさんあります。事前のスコアでハイリスクと分かっている妊婦さんについては、その夫に対する個別指導も重要だと思います。
父親がいないとか、病気や発達障害などで父親の協力が期待できない場合は、他にキーパーソンを見つけて支援者として教育する必要があるでしょう。家族との繋がりも全くない完全に孤立無援のケースでは、産後4~6ヶ月の間は、専門の支援者が常駐するシェアハウスに入って頂くなどの対処が必要になると思います。
シンポジウムの中では「病院も行政もマンパワーには限界があり」といったありきたりな討論がなされていましたが、もっと「日々の生活」に落とし込んだ支援をするには第3者だけが介入してもダメなのです。そして、家族をどのように巻き込んで協力させるかが非常に重要、かつ、マンパワー不足を補うことになるのだと感じました。
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
日付:2017年7月17日 カテゴリー:日々の雑記
「高齢」の呪縛は誰がかけたもの?
今日は自宅のすぐ近くで学会が開催されているので、受けたいセクションだけをちょこっと受講してきました。自転車で会場と自宅を往復できてしまうので、助かりますね。
受けてきたのは「NIPTについて今後の課題を議論する」というパネルディスカッションだったのですが、改めて出生前診断や、高齢妊娠について考えたくなる内容でした。NIPTとは無侵襲的出生前遺伝学的検査(Noninvasive prenatal genetic testing)の略で、母体の血液を採取することで、そこにわずかに含まれている胎児の染色体も一緒に採取して異常がないかどうかを調べるという検査です。正確には「胎児の染色体」ではなくて「胎盤」の染色体なので、胎児自身の体に流れている血液の成分が、母体の採血で採取できるわけではありません。
以前から行われていた「クワトロテスト」や「トリプルマーカー」と比べて検査の精度が高いことから、「新型出生前診断」として話題になったこともありました。現在は、検査を受けられる対象や、検査を行える施設を限定した「臨床研究」という位置づけで、検査の機会が提供されています。要するに、誰でもどこでも受けていい検査ではないですよ、という位置づけなのです。
NIPTの臨床研究については、「NIPTコンソーシアム」のページをご参照ください。
シンポジウムの中では、主に検査の精度について、つまり「疑陽性」や「疑陰性」や「判定不能」の結果が出たケースについて発表されていましたが、パネルディスカッションでの議論の中心は「限定的な検査にすべきか広く誰もが受けられる検査にすべきか」といった内容でした。特に印象に残ったのは、「『偽陽性』が出た場合、本来は正常に産まれるはずの命が失われることになる」という指摘でした。検査の精度的に、「本当は異常がないのに陽性と出る」割合がゼロではありません。たとえ頻度は低くても、「間違って」染色体異常ありという結果が出る場合もあるのです。検査を受けて「異常あり」の結果を受けた方の90%以上が妊娠を中断するという選択をなさっていました。つまり、異常があることが分かったけれど妊娠を継続するという選択をする人はほとんどいないのです。だからこそ、「異常がないのに陽性」と出てしまうことは大きな問題と言えるでしょう。
検査を受けた人の「なぜ検査を受けたか」の理由の9割以上は「高齢妊娠だから」というものでした。年齢とともに染色体異常のリスクは上がります。なので、染色体異常がないかどうかをあらかじめ調べておきたいという理由で検査を受けるという方がいらっしゃいます。検査を受けた方がいいかどうかは、事前の遺伝カウンセリングをきちんと受けて、「万が一異常が出た場合にどうするのか」も含めて夫婦でしっかり話し合ってから個々に決めることです。医師も含めて、当事者以外が「受けた方がいい」「受けない方がいい」ということを示すべきではありません。検査を受けることによって「知らないでいる権利」を一部放棄することになる、ということも含めて、当事者が選択することなのだと思います。
ただ、検査理由のほとんどが「高齢妊娠」であること、そして、年齢を理由に受けた人の9割は正常であるという結果であることを合わせて考えると、「年齢」の捉え方を考え直すべきではないのかと改めて感じました。
高齢妊娠した方や、高齢で妊娠を目指す方は、ぜひ下記の質問の答えをしっかり導いてほしいと思います。
「あなたはなぜその年齢まで妊娠しないという選択をしてきたのですか?」
人によっては「仕事に夢中になっていたら40過ぎていた」「たまたまパートナーが見つからなかった」「病気の治療をしていたらこの年になった」「今まで結婚する気にならなかった」「なんとなくこの年になってしまった」などなど、どちらかというと積極的理由で妊娠する年齢を引き上げたわけではないという方もいらっしゃるでしょう。というか、「好きでこの年になったんじゃないわよ」という方がほとんどかもしれません。
それでもあえて、この質問に答えることに意味があるのです。「なぜわざわざ今の年齢で妊娠した(妊娠を目指した)か?」です。
高齢であることを気にする方のほとんどが、「この年まで妊娠しなかった」ことに罪悪感や後悔など、何らかのネガティブな解釈を持っていることがほとんどです。
妊娠を目指したい理由を書いてもらっても「年も年なので・・・」という方は非常に多くいらっしゃいます。年齢を気にして出生前診断を受ける場合も、ベースは同じ思考回路が働いている可能性が高いのです。
私たち産婦人科医にとっては、年齢と妊娠率や、高齢妊娠のリスクについて正確な情報を提供することも大切なお仕事のひとつです。なので、年齢について色々語ってしまいますが、それらの情報は10代や20代の方たちに「今のうちに知っておいて!今なら間に合うから!」ということで伝えているのです。高齢妊娠の方や高齢で妊娠を目指す方に対して「その年齢まで妊娠しなかったこと」を後悔させたりそれを責めたりしているわけではありません。
高齢妊娠だから何かあったらどうしよう・・・という思いで出生前検査を検討するなら、検査をしない方がよいと言えます。今の年齢まで妊娠をしないという選択をした理由をきちんと考え、「これからの妊婦生活をより安心できるものにしたいから」という理由で受けるのなら、検査の意味があるでしょう。
あなたはまだ「年齢の呪縛」を大事に持ち続けますか?それとも、上記の質問にサクッと答えて、さっさと手放しますか?
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
日付:2017年7月16日 カテゴリー:不妊症,日々の雑記
女性アスリートのサポートは10代こそ重要なワケ
女性アスリートをサポートする時に気を付けなければいけない点、つまり女性アスリートに起きやすい医学的トラブルは次の3つだと指摘されています。
*低栄養(低体重)
*骨密度低下(とそれに伴う骨折)
*無月経
これらを女性アスリートの3主徴と言いますが、一つ一つが独立した問題ではなく、低栄養だから骨密度が下がり、体重が減りすぎて無月経にもなり、無月経のせいでホルモン不足になって骨密度が下がりやすくなり・・・と、3つの状態がループを描くようにお互い関連し合っているのです。
特に「骨」の問題は、医学的介入するタイミングを逃すと、十分な回復の機会を失ってしまうことになりかねないので、早期にその兆候に気付いて適切な治療や改善を行っていくことが重要です。無月経にともなう女性ホルモン不足は、骨密度の低下を引き起こしますが、それに対して10代のうちにホルモンを補えば骨密度はある程度回復しますが、20代になってからホルモンを補っても骨密度があまり変わらないというデータがあります。また、アスリートに限らず、何らかの影響で無月経になってしまった場合の骨密度の下がり具合は、10代のまだ骨量がピークを迎える前に無月経になった場合は明らかに骨密度に影響が出ますが、20歳以降に無月経になった場合は骨密度はあまり下がらないというデータもあります。
つまり、骨密度がピークを迎える18歳くらいまでの間に女性ホルモン不足の状態が続くと骨密度に影響が出やすいから、10代の無月経や骨密度低下には早めにホルモン補充などの治療的介入が必要ですよ、ということです。
個人的には、10代のうちは月経不順になる方も多く、また自分の体との付き合い方も十分に把握できておらず、コーチに言われるがままにハードなトレーニングや減量を行ってしまうリスクも高いのではないかと感じています。また、コーチの性別にもよりますが、月経不順や無月経になってもコーチに言わずにいる(言い出せない)というアスリートも多いというデータがありますから、いかに指導する側が正しい知識を持ってアスリートのヘルスケアを行うかということが重要になります。
私は、自分の経歴的にダンサーの方を拝見することも多々ありますが、特にバレエダンサーに「医学的適正体重」を示すだけではサポートにはなりません。医学的許容範囲と、本人が美容的に、そしてトーで立った時の足首の負荷的に許容できる範囲を探って適切な栄養指導を行っていくことが重要なのだと感じています。
低用量ピルや超低用量ピルは、ホルモン補充の目的でも月経日のコントロールの目的でも活用できて、しかもドーピングには引っかからない薬剤になっていますから、本来はもっと女性アスリートの方に活用していただきたいものなのですが、まだまだ日本人のアスリートにピルの活用は浸透していないようです。
若年者のアスリートやダンサーの指導に当たる方へのアドバイスも行っております。ご希望の方は、クリニックにお問い合わせくださいませ。
045-440-5567 info@be-proud-07.sakura.ne.jp
日付:2017年7月13日 カテゴリー:日々の雑記
薬を「どのような意識」で使うかが重要なワケ
クリニックの問診票には、「どのような治療をご希望ですか?」という質問も書いてあります。また、何か治療が必要と思われた時は、標準医療としての選択肢をお示しして「ご自身がどうしたいというご希望がありますか?」と質問するようにしています。
これは、「すべて先生にお任せします」という、受け身な姿勢を作らないためです。上記の質問をしても「よくわからないのでお任せします」と言われてしまうこともしばしばありますが、現状と治療のメリット&デメリットを総合的に考えて、まずこういう方法をとるのがいいと思われますがどうしますか?、と食い下がります。最終的に、患者様が「自分で」治療法を決めるということがとても重要だからです。
人によっては「できるだけ薬を使いたくない」「薬に頼るのは嫌だ」という方もいらっしゃいます。ネット情報でも、薬の副作用が色々書いてありますし、「抗がん剤のせいで寿命が縮む」といった内容も散見されます。
でも、同じ薬を使っても、副作用が強く出て効果が感じられない方もいらっしゃれば、副作用は全くなく劇的に症状が改善する方もいらっしゃいます。この差は何なのだと思いますか?
実は「薬」そのものが悪いのではないのです。前回の記事の、コンビニの食品そのものが悪いのではないのと一緒で、その薬をどういう意識又は目的で使うかがカギなのです。
多くの場合、薬を用いる時は「辛い症状を緩和させたい」「これを使わなければもっとひどくなるかもしれない(という不安)」など、何か「避けたいことを避ける」目的で使ってしまいがちです。また、「医者に勧められたから」「ほかに選択肢がないから」「やめたら死ぬかもしれないから」など、受け身又は依存的理由で使う方も少なくありません。
これらは、問題回避行動で受け身なのでうまくいかないパターンなのです。
例えば、ピルを使う場合も「受験があるからそれが終わるまでは月経をコントロールしておきたい」「数年後に妊娠を希望しているから今のうちに整えておきたい」など、未来にある何らかの目標に向かって、自ら薬を「活用する」という意識で使う場合は良い結果が得られます。
私も長年ピルを服用していますが、月経を自らの意思でコントロールする=自分の人生に対して主導権を握る、ために服用しているので、副作用は全くありませんし月経を好きな時に来させているのでとても快適です。
このように、薬を「どのような意識で使うか」はその副作用や効果の出かたに影響します。
あなたは、問題回避や受け身な立場で薬を飲んでいませんか?もし、その薬を「やめたいのに…」と思いながら仕方なく飲み続けているのだとしたら、早くやめる方法を選んだ方が賢明です。
クリニックのカウンセリングでは、こういった「本当はやめたい薬」をやめるお手伝いもさせていただいています。
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
コンビニ総菜が体に悪い本当のワケ
コンビニで購入したおむすびやサンドイッチが「腐らない」とか「カビが生えない」ということはよく指摘されます。コンビニのものだけでなく、袋に入ったパンなども「カビが生えない」と言われていますが、なぜ腐らないしカビも生えないのかということに対して、「防腐剤や消毒薬が使われているからだ」(だから危険だ)という意見と、「衛生管理がしっかりしているからだ」(だから安全だ)という意見があります。
コンビニのお惣菜がどのような過程でパッキングされるのかは実際に工場の中に入って働いたことがあるので、完全に無菌状態でないことは明らかです。本当に何の防腐剤も使用されていないかはご想像にお任せしますが、少なくとも衛生管理だけで何日も何か月も食品が「腐らない」というのは、自然な形ではないことは想像できるでしょう。もし本当にパッキングの技術が高度で、清潔にパッケージに入れられているから腐らないのだとしたら、パッケージから出して数日間常温保存してみればよいのだと思います。
コンビニのお惣菜が「何となく体にはよくなさそうということは分かっていても、それを完全に科学的に証明したり、コンビニのお惣菜だけを食べ続けた場合にどの様な病気になるのかを検証することは難しいかもしれません。
患者様の中に、コンビニでバイトをしているので、毎日賞味期限ギリギリの残り物をもらって食べているという方がいらっしゃいましたが、不定愁訴が多々あり、血液検査では軽度の肝機能障害と明らかな栄養不足がありました。この状態が、コンビニの食べ物のせいだけで引き起こされたのだといことを証明することは難しいでしょう。でも、コンビニの食べ物を一切やめて食生活を改めていただいたら、出ていた症状は軽減されました。
私自身は、コンビニ食やカップ麺などのインスタント食品、そしてファストフードなどは、「健康を害する食品」として認識しています。よほどの非常事態でなければ極力口にしませんし、子どもたちにもできる限り与えません。コンビニもファストフード店もそこかしこにあふれているので、まったく食べさせないということはなかなかむつかしいのですが・・・
なぜこれらの食品が「健康を害する」可能性があるのか、それを科学的に証明することにあまり意義を感じていません。なぜなら、これらの食品を選択している時の「脳の動き」がすでに病気を作り出す脳になっているからです。
ある美容家の方がこうおっしゃっていました。
「コンビニコスメが悪いわけではありません。コンビニコスメの中にも効果が高いものがあるかも知れません。問題は、自分の美しさに対して『コンビニコスメで済ませてしまえ』という姿勢です。その気持ちが、美からあなたを遠ざけます」
コンビニコスメを上記の食品に、「美」を「健康」に置き換えて考えてみてください。あなたが上記の食品を口にする時、それが世界一美味しい食べ物でどうしても欲しいから食べたい、という気持ちで口にしているでしょうか?どんな時に上記の食品を選択しているか、思い浮かべてみるとわかりやすいでしょう。
人は自分が口にしている食べ物と、口にしている言葉で成り立っています。つまり、自分の体の源となる食べ物を「コンビニ程度のもので済ませてよい」と認識していると、健康状態がどうなっていくのかを考えていみるといいでしょう。
産後うつ予防に必要なものは?
産後数日から2週間以内に起きる、精神的な抑うつ状態は「マタニティーブルース」と言って、比較的多くの方に見られるものです。産後のホルモンの変動や、慣れない赤ちゃんのお世話、想像を超える自分お体の変化などによって、一時的に「ブルー」な気分になってしまうのですが、たいていは2週間以内に治まります。それが、2週間たっても改善しなかったり、「なんとなく落ち込みやすい」レベルではなく、育児もままならなかったり自分の食事や睡眠もまともにとれないレベルになってしまったら、それは「産後うつ」という状態です。
産後うつは、産後すぐになるとは限らず、数か月たってからその症状が出てくることもあります。産後うつを放置してしまうと、育児放棄や自殺など大きな問題につながってしまうこともあり、産後うつをどうやって早期発見するかが重要と言えます。産後の健診は1か月で終わってしまため、数か月後に産後うつになっても誰も気づくことができないというリスクがありうるのです。
自治体によっては、1か月健診後も医療機関とのつながりを保てるようなシステムや、保健師さんや助産師さんの家庭訪問を受けられるシステムもあります。これらをうまく利用して一人で抱え込まないことは、産後うつから早く抜け出すには重要なのですが、実際に産後うつになっている人が果たして自ら健診を受けに出向いたりできるのか疑問でもあります。
産後に限らず、「うつ」という状態の背景に隠れているのは「自分はもつ権利がないと思っている怒り」です。つまり、ぶつけどころのない怒りや理不尽な思いを「抑え込もう」としてため込んでいるとうつになるのです。
産後にうつ状態になりやすいのは、この「ぶつけどころのない怒り」を感じる対象が赤ちゃんだからです。さっきおむつを替えたばかりなのにすぐウンチをしてしまったり、授乳し終わったのに寝てくれなかったり、1時間おきに夜泣きをしたり、せっかく作った離乳食を食べてくれなかったり・・・産後は赤ちゃんに対して「もう!なんでよ!」と言いたくなるシーンは山ほどあります。でも、そんな怒りを赤ちゃんにぶつけるわけにはいきません。それどころか、周りからは「泣いていてもかわいいわよね」と言われて、赤ちゃんに怒りや理不尽さを感じてしまう自分を「母親失格」と責めてしまったりするわけです。
そんな怒りや理不尽さを、何とかしてなかったことにしようと抑え込んでいると、うつ状態になってしまいます。産後うつを予防する最も効果的な方法は、身近な人にこの理不尽な思いを「理解してもらう」ことではなく、ガンガンぶつけられる「サンドバック」になってもらうことです。赤の他人にそのような思いを遠慮なくぶつけるということは難しいでしょう。だから、サンドバックとして最も適任なのは「夫」のはずなのです。
ところが、夫がサンドバックになってくれないどころか、そもそも「家にいない」状態の家庭が増えているために、産後うつのリスクも増えています。産後数か月たってからうつ状態になるのも、生まれてしばらくは物珍しさも手伝って育児に参加してくれていた夫が、途中から飽きてきて仕事に逃げ始めたり、妻の理不尽な感情の爆発を受け止めきれなくなってしまうからです。
夫が果たすべき最も重要な役割は「イクメンになる」ことではありません。妻の、本当は赤ちゃんに向かってぶつけたい様々な怒りや理不尽な思いを、ひたすらサンドバックになって受け止め続けることです。その思いを心から理解しようとしたり、解決策を見つけようとしたりする必要はありません。受け止めて「よしよし」とするだけでよいのです。
今産後うつで困っている人は、まずは誰でもよいので「サンドバック」を見つけましょう。夫でなくてもよいのです。母親でも、地域の保健師さんでも、友達でもいいでしょう。まずは抑え込んでいる怒りをぶつけること。それが、うつから脱却する第一歩となります。
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
日付:2017年6月25日 カテゴリー:日々の雑記
なぜ親が親としての役割を果たそうとするほど子どもに病気が出やすいのか
体重減少性無月経と母親の過干渉との関係などは以前から指摘されていますが、親子関係が婦人科疾患を引き起こす背景に隠れていることは珍しくありません。母親の過干渉を、娘さんご本人が息苦しいとか「嫌だ」と自覚している場合は、解決の糸口を見つけやすかったのですが、いわゆる優等生タイプや「いい子」を演じてしまうタイプの方だと、質問をしてもあまり親に対する反発心もなく、どのような関係性が隠れているのか見つけにくいことがしばしばありました。
最近、過干渉な母親⇔従順な娘の関係の中で何が起きているのかがだんだん見えてきました。母親が「母親たるものこうでなければいけない」と思って「ちゃんと母親をやろう」と思えば思うほど、そして、娘さんが「いい子になろう」「親を尊敬しよう」とすればするほど、月経不順や月経困難症を引き起こしてくるのだということが分かってきました。
ご本人が親を尊敬したり「親として」感謝していたりするので、一見問題点が見えにくくなるんですよね。でも、「子どもは常に親の望みを叶えようとする」という観点から見てみると、解決の糸口が分かってきます。
母親が過干渉な場合、親の潜在意識下の望みは「親としての役割をこなしたい」つまり、子どもに対しては「子どもとして庇護下に置いておきたい」ということになります。親が親として「ちゃんとやろう」と思うことは、一見悪いことではないように思えるかもしれませんが、実はこの「親の望み」を叶えるためには、子どもは「子どものままでいる」必要が生じるのです。
女性の場合、子どものままでいるとはすなわち卵巣機能を押さえておくということです。または、「子宮や卵巣なんていらない!」と思うような現象を引き起こすということです。これが、月経不順や月経痛という症状で現れているのだということが、何組もの母&娘関係を見る中で明らかになってきました。
「親らしくあろう」「子どもらしくあろう」と思うことが「悪いこと」であるという意味ではありません。ただ、「親らしく」の中身が「親なのだからこうあるべきこうあってはならない」という「べきべき思考」から発生している場合、親らしくあろうとすればするほど「本来の自分の姿」からずれてしまう場合があります。
また、そんな親の無意識の望みをキャッチして、子どもが「子どもらしくあり続けよう」とすると、子どもの自立や精神的にも肉体的に成長することを抑えることになります。「思春期」と呼ばれる時期は、親子関係に何も問題がなくても、子どもが子どものままでいたい気持ちと大人になりたい気持ちがあいまざって揺れる時期です。この時期に月経不順やひどい月経痛が発生するのは、子どもらしく「在らねばならない」という意識が悪さしている可能性があります。
最近は、こういったケースに対して、親に働きかけてもなかなか意識が変わらないので、ご本人だけに診察室に入っていただいてアプローチするようにしています。
10代の月経不順の患者様は、一生懸命親を「尊敬しよう」としていらっしゃいました。でも、本人の「自分らしい生き方」は母親の生き方とは全く別だったんですね。母親と「違う選択」をすることがどうしても抵抗があるようだったので、「お母さんと違う人生を歩むことと、お母さんの人生を否定することはイコールではないよ。違う選択をしても、お母さんの人生はお母さんの人生として尊重していることになるんだよ」とお話ししたらぽろぽろ泣いていらっしゃいました。
この親子関係を「よりよくする」方法は簡単です。双方が「自分らしく」生きればいいだけのことなんです。親だから、子どもだから、という枠を取り払ってみた時、自分は「どうありたいのか」「何がしたいのか」を基準に生きるということです。
「自分らしい人生」の中に「母という役割をしっかり楽しむ」が入っているのであればそれをやったらいいですし、そうでない人生を選択したかったらその道をまっすぐ進めばいいのです。お互いが「こうあるべき」役割を確認し合っていても、どちらも幸せにはなれません。まずは「あなたから」先に、自分らしい人生を歩み始めてはいかがでしょうか。
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
日付:2017年6月20日 カテゴリー:日々の雑記
産まれた意味を自分で「つけ直す」
先週になりますが、私のカウンセリングの師匠が主催する「リ・バース」というセミナーを受講してきました。タイトル通り「産まれなおす」というワークをとことん繰り返して、今までの自分の人生に起きた出来事を「ある存在」になって意味づけしていくという作業を行っていきました。
自分がなぜ今の両親のもとに生まれたのか、なぜこれまでの人生を歩んできたのか、一つ一つの出来事に解釈をつけ直して、その先にある未来を見つめ直すという作業でした。私にとっては、特に幼少期から感じていた「ある感覚」の意味に気付くという非常に大きな気づきを得たセミナーでした。本当に、人生の意味付けが根底からひっくり返るくらいの重要な感覚を取り戻したのです。
テキストの冒頭にこう書いてあります。「振り返った時に初めて人生を理解することができる。しかし、人生は理解する前に生きるようになっている。」まさに、その通りなのです。だから、人生を振り返るのは「死ぬ時」では遅いのです。でも多くの人は、振り返って愚痴を言うことはあっても、そこに未来につなぐ意味付けをするという作業は行いません。
ワークの中には、「なぜ自分は今の両親を選んで生まれてきたのか」を見つめ直すワークもありました。これをやりながらふと、母の日に「感謝を強要される子どもがかわいそう」という書き込みをいくつか目にして、非常に違和感を覚えたことを思い出しました。
2分の1成人式や、母の日・父の日のイベントに対して、「産まれたことに感謝できない子もいるのに」「親に感謝したくない子もいるのに」という指摘が散見されます。個人的には、「感謝すること」は他人から強要されることではありませんし、わざわざ学校単位で一人一人発表するようなことはしなくていいと思っています。同時に、親に感謝することは自然なことで、そのイベントそのものを否定する必要もないと考えています。「あなたはどんなことに感謝したいですか?」と問いかけることによって「感謝したいポイント」を探すアンテナが立ちます。その問いかけを小さい頃から行うことに意味はあるのです。
様々な家庭環境や出生状況がある中で、それらの多様性に配慮した教育プログラムは必要でしょう。でも、私が感じた違和感は、そうした「過剰な配慮」が「かわいそうな子」を生み出しているのではないかといことです。
「リ・バース」のセミナーの中には、症例として虐待を受けていた方の事例も紹介されました。その方にとって、虐待も「親に愛されていない」という感覚も、あることに気付くために必要なことだったのです。そう、その方にとって必要なことが必要な形で起きていて、そして、本人がその事実をどのように「解釈するか」で未来が変わりました。
家庭環境や現在の環境的に、親に感謝するどころか「なんで自分を産んだんだよ!」と文句を言いたくなったり、感謝なんかするものかと思う人もいるかもしれません。今は、自分の置かれた環境にただただ悪態をつくしかできないかもしれませんし、死にたいと思っている人もいるかもしれません。
そのような状況の人に対して、周りが「かわいそう」「感謝なんてしなくていい」という意味付けを与えてしまっては、その人が自分の人生の本当の意味に気付くチャンスを奪うだけのような気がするのです。
感謝をするか、文句を言い続けるかも本人の選択です。どんな母親であっても「お腹の中で育ててこの世に命ある形で生み出してくれた」ということは事実ですし、それに対して「産まなければよかったじゃないか!」と否定し続けるのも、「産んでくれただけで感謝」と思うのも自由です。どちらの意味を「自分の人生」に対してつけるかで、その後の人生は大きく変わりますから、どのような人生を歩みたいのかを考えて今の自分に意味づけをしていけばよいと思います。
私は、虐待を受けている人に対しても、「産まれなきゃよかった」と思っている人に対しても、「かわいそう」とか「恵まれない環境」といった解釈を持っていません。そんな意味付けは本人にとってためにならないからです。
母の日も2分の1成人式も、やり方を変えれば、早い段階で自分の生まれた意味を「つけ直す」チャンスになるのですけれどね。優しい振りをして、本人が「リ・バース」するのを妨げていないか、周りの大人が振り返ってみる必要があるのかもしれません。
日付:2017年5月30日 カテゴリー:日々の雑記
なぜワンオペ育児はなくならない?~見えにくいジェンダーバイアス~
ムーニーのCMが「ワンオペ育児を賛美している」と指摘されているようですが、「賛美」しているかどうかはともかく、このCMを見た時、私自身も感動したり「よし頑張ろう」と思うどころか、「これじゃあ辛いママがもっと辛くなってしまう」と感じました。だってあまりにも悲惨な状況なのに、誰の手も借りれずに、ひっそりと泣いて、そして最後が「その時間がいつか宝物になる」ですから・・・宝物になる前に自分が壊れるんじゃないの?と突っ込まずにはいられません。
CMに対する評価はこちらをご参照くださいませ。
CMの中でいくつか突っ込みどころ満載のシーンが出てきます。突っ込みたくなるのは、CMを作成している会社に対してではありません。「こういう現実を作っている男性、多いよね」という「お父さん」達への突込みです。
*夜泣きで眠れない→お父さんは別室でぐっすり?たまには交代したら?
*赤ちゃん抱っこして重い買い物→お父さんが帰りに買い物くらいしようよ
*赤ちゃんが泣いてお風呂もゆっくりつかれない→妻が入浴中の10分くらいお父さんがあやそうよ
*自分の食事もままならない→お昼ご飯は無理として朝食と夕食は交代で抱っこすれば食べられるでしょう
*自分のお肌の手入れもできない→妻がお化粧する5分くらいお父さんが抱っこしとこうよ
CMの冒頭にちらっとだけお父さんがうつるので「あ、シングルマザーを描いてるんじゃないんだ」と気づけますが、ほぼシングル状態ですよね。
これ見て、「うちもこんなだった~」「今まさにこんな状態です」という感想が多数寄せられているということは、日本全国のママたちの多くがワンオペ育児で奮闘しているということなんだと思います。逆に言えば、ワンオペ育児を妻にさせている夫が多数いるということです。
なぜこのような状況が何の疑問も持たずにまかり通ってしまうのか、その背景には非常に見えにくい形でのジェンダーバイアスがはびこっているからだと思われます。ジェンダーバイアスは自分の親や「世間」から知らず知らずに刷り込まれるのでそれが「当たり前」だと思い込んでしまって気づきにくくなっているのです。
例えば、次のシチュエーション、何がおかしいかわかりますか?
共働きの夫が「妻の負担を減らすために夕食のおかずを買ってきてやったぞ」と自分が食べたいものを自分の分だけ買ってきました。妻は「ありがとう、助かった」と言いました。
さらっと読むと、何も変だと感じないかもしれません。実はこれ、我が家で発生したやり取りです。
では、これを妻と夫を逆にして読んでみてください。
共働きの妻が「夫の負担を減らすために夕食のおかずを買ってきてやったぞ」と自分が食べたいものを自分の分だけ買ってきました。夫は「ありがとう、助かった」と言いました。
何が変だか気づきましたでしょうか?入れ替えると、最後の夫のセリフが違うものになるかもしれません。そもそも、なぜ自分の食べ物を自分で買ってくることが「妻のため」なのでしょうか?
では次のシチュエーションはいかがでしょうか?
日曜日にセミナーに参加した妻にほかの参加者がこぞって「あら?今日はお子さんは?」と聞きました。妻は「今日は夫が見てくれているんです」と言いました。周りは「素敵なご主人ね~」と言いました。
これ、実はよく見かけるやり取りです。日曜日でなくても、小さい子がいる母親が一人で出かけるとたいてい聞かれます。
では、これも妻と夫が逆になったらどうでしょう?
日曜日に趣味のゴルフに出かけた夫にほかの参加者が「今日は子どもはどうしたんだ?」と聞くでしょうか?「妻が面倒て見ている」という答えに「お前の奥さんホントすごいよな」というでしょうか?
これらはすべて、食事の支度などの家事や子どもの面倒を見ることが「妻の役割」として認識されてしまっているから発生するものです。夫も周りも、そして妻本人も妻がやるのが「当たり前」だと思っているんですね。
だから、家事をしなかったり子どもを預けて仕事や趣味の時間を作ると「申し訳ない」という気持ちになってしまったり、時にはそれを責められたりするんです。だからワンオペ育児も「私がやるべきことなのにちゃんとやれなくてごめんなさい」と一人でひっそり泣いて、「母親なんだから強くならなきゃ」で頑張り続けることを自分で自分に強いることになってしまうのです。
ワンオペがダメだと言ってるわけでも、家事を夫婦で分担「すべき」と言ってるわけでもありません。分担の割合は、各家庭によって異なるでしょうし、我が家のように夫の仕事の状況と気分によって3:7の時もあれば9:1の時も発生したりするかもしれません。
私は、このジェンダーバイアスに気付いて、女性に楽になってほしいと願っています。上記のように夫が自分の分だけ買ってきたら「ありがとう」ではなく「なんで?私のは?」って言っていいんです。日曜日に夫が育児をすることを「父親なんですから子どもを見るのは『すごいこと』じゃないですよ」と言っていんです。自分が「やるべきこと」だと思い込んで抱えているものを、やらなかったり人に任せたりしていいんです。
ジェンダーバイアスは私の中にもまだたくさん潜んでいると思います。気づくポイントは上記のように男女を入れ替えて考えてみることです。入れ替えてみると何が変なのかがすぐにわかります。それに気づいたら「あ、変な思い込みしてた」と「枠」をひとつづつ外していけばいいんです。そうして、「堂々と自分のために」日々を過ごしましょう。
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
日付:2017年5月25日 カテゴリー:日々の雑記