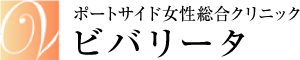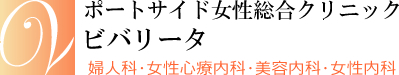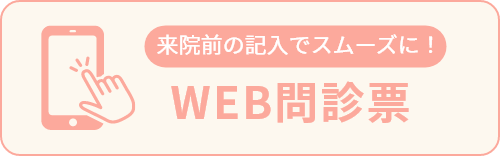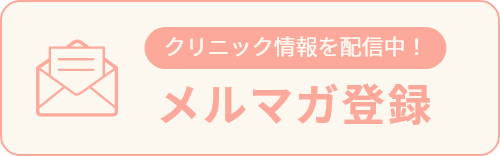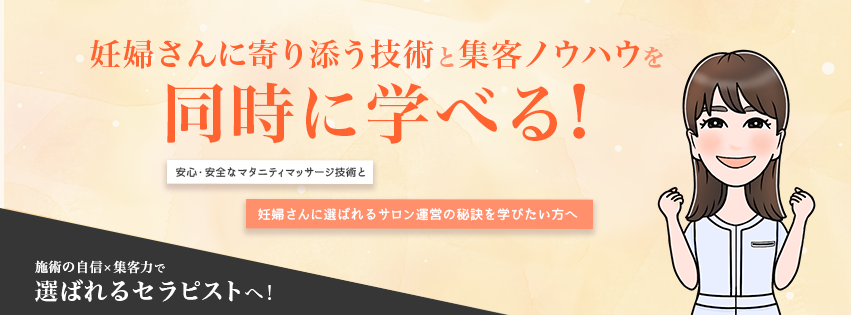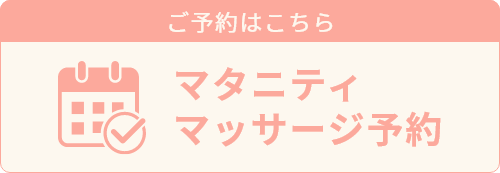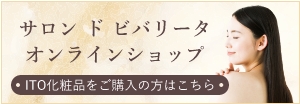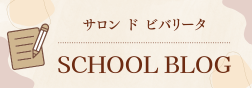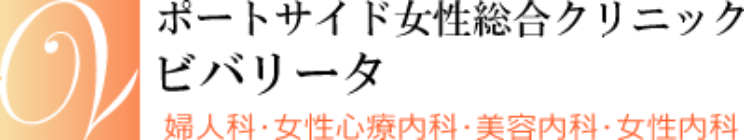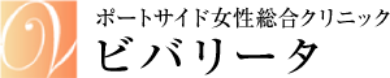日々の雑記
妊娠したいのにできない本当の理由
シークレット・スライト・オブ・ランゲージの視点で「病気」を見ると、病気も無意識のうちに本人が望んだ結果なのだということがよくわかります。
病気の場合、その病気になる「メリット」が存在することが多いように感じています。実は、先々週末から1週間次女が体調不良で保育園をお休みしていたのですが、それを見ていた長女はずっと自分もお熱を出して保育園をお休みしたいと言っていました。そして、見事に(?)先週末からお熱を出してこの3日間保育園をお休みしています。長女にとっての病気になる「メリット」は、保育園をお休みできるし、お母さんは妹より自分を優先して優しくしてくれるし、ご飯を食べなくてもアイスクリームがもらえるし、いいことだらけなわけです。でも、頭痛と口内炎による痛みが辛いらしく、「明日にはお熱治る?」と言うので、「保育園休めるけど頭痛いのと、元気になって保育園行くのとどっちがいい?」と聞いたら、「元気になって保育園お休みするのがいい!!」とのこと・・・(笑)
妊娠したいのになかなか妊娠しない場合や、不妊治療を行っているのに治療が思うように進まない場合も、同じことが言えます。
不妊の場合、まず最初にチェックした方がいいのは「何のために妊娠したいと思っているのか」です。妊娠が「目標」ではなく「手段」になっていないかをしっかり見極める必要があります。例えば、「パートナーの心をつなぎとめたい」とか「親を喜ばせたい」とか「産んでないという劣等感を払しょくしたい」とか「妊娠できないかもという不安をなくしたい」とか「過去に産んであげられなかった罪悪感を消したい」といった、妊娠を何らかの手段にしようとしている場合、そもそもゴールの設定が「妊娠」ではないのでうまくいきません。
私が長女の妊娠を目指し始めた時、実は末期がんの父親を看病しているところでした。「花嫁の父」という大役を終えた後、父の次の「楽しみ」を作りたいと思って、早く「孫が生まれるよ」と伝えたくて焦って妊娠を目指していたんですよね。でも、その時は全然卵が育たなくなって結局妊活をいったん中断せざるを得なくなりました。父が亡くなってちょうど1年後に、長女が誕生したのです。
次にチェックした方がいいのが、「妊娠・出産によってもたらされるデメリット」です。女性は妊娠したら「今まで通りの生活」は続けられなくなることがあります。産後も、体調が十分に回復しなかったり、思うように職場に復帰できなかったり、育児のストレスにさらされたり、ちょっと考えただけでも多くのデメリットが挙げられてしまうのではないかと思います。特に、妊娠経験や出産経験がある方は、初めての方よりもそのデメリットを強く感じる可能性があります。最初の妊娠でつわりがひどくて辛い思いをしたとか、お産が大変でその後体調不良が続いたといったケースでは、「また同じことが繰り返されるのか」という恐怖が潜在的に残るからです。
何にデメリットを感じているのかは、夫婦でシェアし合うということがとても重要になります。特に女性側の感じていることを、パートナーに知ってもらうだけでも、具体的な解決方法を2人で探してみたり、「理解してもらえた」という安心感がそのデメリットを薄めてくれる効果が期待できます。
そして、もう1つ忘れてはいけないのが「妊娠・出産しないことによるメリット」のチェックです。不妊治療を続けている方の中に、よくよくお話を伺うと「私はそんなに子どもが好きではないんですけれど、夫がどうしても子どもがほしいというので」という方もいらっしゃいます。この場合、「不妊治療までしたけど妊娠できなかったの」という結果を提示することで、「本当は子どもは欲しくないの」と言わなくて済むわけです。
また、人工授精を繰り返している方で、「夫とのセックスが嫌」という方もいらっしゃいました。人工授精だと、セックスしなくても妊娠は目指せるんですよね。治療中であることが、セックスを断る口実にもできます。もし私が、この方を今担当していたら、「妊娠中や産後は医師から堂々と『セックス禁止』って言ってもらえますよ」とささやくかもしれません。
妊娠できない本当の理由を探すポイントは、他にもいくつかあるのですが、まずは重要な3つのポイントを挙げてみました。
もし、自分ではうまく原因が探し出せない、または原因は分かったけどどうしたらいいのか分からない、という場合は健康サロン(http://be-proud-07.sakura.ne.jp/vivalita.com/salon/healthcare.html)でカウンセリングも承っていますので、お気軽にご相談ください。ご予約・お問い合わせはメール(info@vivalita.com)でお願いいたします。
日付:2015年10月29日 カテゴリー:不妊症,日々の雑記
自分の「人生のハンドル」は自分で握る
昨日のブログの中で「他者原因」と「自分原因」について書きましたが、実は以前違うセミナーでも同じような内容のお話を聞いていたんですよね。それは、女性のリーダーシップについてのセミナーでしたが、最初に「人生におけるリーダーシップとは」というお話しの中で、自分の人生に対する姿勢には2種類あって「リーダー」になるか「被害者」になるかのどちらかなのだということをお話しされていました。
「リーダー」の立場に立つというのがすなわち「自分原因」で物事を見るということです。人生の主役は「自分」であり、自分から出来事に対して働きかけていきます。一方、「被害者」の立場に立つと「他者原因」で物事を見ることになります。主役が自分以外の出来事や他人になってしまい、起きた出来事や現状に不満を言うだけで自分からは何も働きかけない状態です。
「リーダー」よりも「被害者」の立場に立っている方が自分の人生に対して責任をとらなくて済みます。「未来行の車」のハンドルを他人や病気やお金に握ってもらっている状態です。自分の行きたい方向と違う方向に行ってしまったら、そのハンドルを握っているものや人に対して、ただ文句を言えばいいわけです。でも、ずっと行きたい方向にはいけないままになります。
「リーダー」の立場に立つということは、未来行の車のハンドルをしっかり自分で握るということです。そして、目的地はどこなのか、そこにたどり着くためのルートはどのようなものがあるのか、ルートを間違えないようにするための「目印」はどこにあるのか、どのくらいの時間をかけて目的地に行けるのか、などを全部自分で考えて自分で舵取りをするのです。「被害者」の立場に立つよりも、自分の人生に責任を持つ必要がありますから、ある意味腹をくくる必要があります。でも、「自分の人生」を取り戻すためには、自分でハンドルを握るしかないのです。
私が長女の妊娠のタイミングを考えた時、どうやっても開業の時期と重なってしまうことが予測されました。開業を延期することもできますが、いつ妊娠が成立するかわからない状態でそれをやってしまうと、ズルズルと先延ばしになってしまう可能性があります。一方、妊娠を先延ばしにすると、年齢的に妊娠しにくくなるリスクがありました。
なので、私は妊娠と開業の両方を同時進行すると決めたのです。一般常識からしたら「ありえない」選択なのかもしれません。でも、私は医師としての自分も女性としての自分も両方尊重したかったんですよね。
開業して半年後に出産を控えるというのは、1人院長で診療している状態ではたくさんの「問題」が発生します。予定日が近づいてもなかなか非常勤の先生が決まらなかった時、私は「最悪の場合入院期間中は患者さんに『ごめんなさい』と言って病院をしめればいいんだ。その間売り上げが落ちた分は後から取り戻せばいいんだ。それ以上の悪いことは起こりえない」と腹をくくりました。そうしたら、奇跡的に非常勤の先生が見つかり、出産の8時間前まで働いて、病院について1時間半でスルッと産まれ、超安産だったため退院の翌日から診療に復帰することができました。全部「何があっても自分で責任をとる」と決めたからこそ起きた「結果オーライ」だったのだと思います。
もし今、「この〇〇さえなければ自分の人生うまくいくのに」と思っている人がいたら、それはその〇〇に自分の人生のハンドルを握らせているということです。今すぐ運転席を交代しましょう。運転の仕方が分からなかったり、目的地が分からなかったりするかもしれません。でもまず最初に必要なことは、しっかり自分でハンドルを握ってみることなのです。
日付:2015年10月28日 カテゴリー:日々の雑記
子育ての大変さをコントロールしてみる
この週末は、シークレット・スライト・オブ・ランゲージの3~4回目を受講してきました。
隔週で土日を確保するのは、ミュージカルの練習に通っていた時と同じように色々「段取り」が必要だったりするんですが、それでも受ける価値が大いにあると感じたセミナーなんですよね。
今回からは、ペアを組んで具体的なセッションの練習をし、それをビデオに撮ってみんなで見ながら「ここでこんな介入ができたよね」「この内容をもっと掘り下げた方がいいよね」といったフィードバックをしていきます。
ペアで練習していくわけですが、今自分が抱えている悩みをカウンセリングしてもらうようなものなので、勉強しながら自分もクライアントとして治療していただいているような感じです。
昨日の練習で私が取り上げたテーマが「人間らしく食事をしたい」というものでした。
冒頭で私が「人間らしく」といった時点で講師の先生から突っ込みが・・・「人間らしく食事をしたい」ということは、すなわち「人間らしくない食事を強いられている」つまり、自分のコントロールのできないところで強制的にその状態を「押し付けられている」という信じ込みがあるわけです。食事に限らず、子育てにおいて私は「自分でコントロールできない」ということにストレスを感じていました。そして、自分の「望まない生活」を強いられていると感じていたんです。それを象徴する言葉が、子供たちと丸一に過ごした時の「奴隷生活」です。
この「自分ではどうしようもない」という受け身の姿勢を専門的に分析すると「他者原因」で「反映分析型」といいます。要するに、困った状況を作り出している原因を「自分以外(私の場合は子供たちや夫)」に見出したり、困った状況に対して「自分から働きかけることができない」と判断している状態です。
そのことを指摘されたとき、正直「なんでだろう?」とかなり違和感を感じました。なぜなら、育児に関わるとき以外は私はどちらかというと原因を自分に見出して、自己責任としてその問題に対応したり、どうすれば解決できるかに焦点を当てて自分が主体的に働きかけることができるからです。でも、育児にかかわる部分だけ、「私の力が及ばない」という信じ込みが必要だったんですね。
なぜ、育児に関して「自分原因」にすることに抵抗があったのか、それは「自分原因」にすると「育児の大変さを周りに理解してもらえないままになる」というデメリットがあったからです。育児が大変だと感じるのは「私の問題」で、本当は育児なんて「全然大変じゃないんだよ」ということになると、ものすご~く不都合があったのです。
ちょうど、育児の大変さを訴えたら「好きで生んだんでしょ?」と言われて追いつめられるのと似た心情だと思います。子供がほしいと思って自分が望んで生んだ、ということは間違いありませ。でも、「今の生活を望んだわけではない」ということが理解されないから、「好きで生んだんでしょ」と言われるとショックを受けるわけです。
育児は大変さがあるのが当たり前なんです。それをどの程度「苦痛だ」と感じるかに個人差が大きくて、あまり苦痛でないと感じる人は「大変さもあるけど楽しい」と言いますし、苦痛が大きいと感じる人は「子供の笑顔で帳消しになんかならない」と言うわけです。ちなみに私は後者です。なぜ後者になるのかは、またの機会にお話ししましょうか。
じゃあ、なぜ私が育児の大変さを「わかってほしい」と感じていたのか、それは私がどれだけ育児を頑張ってるのかを認めてほしいという気持ちが背景にあったのだと思います。夫に「わかってほしい」と思っていたのと同じように、周りに「わかってほしい」と思うのは、私が自分で自分をほめてあげられていなかったからなんですね。
そのことに気付いて、私ってこんなに子供のこと思ってるじゃない。子供のためにも頑張ってるじゃない。もう、十分だよと思ったら、涙が止まらなくなりました。その状態で冷蔵庫の前で泣き崩れていたら、次女が「だいじょ~ぶ?」と言いながら頭をなでに来てくれました。次女は私に似てとても勘が鋭いのです。
食事の時間が、2人の娘の相手で戦争状態なのは変わりません。でも、それを「人間らしくない食事」ではなく「3年限定の実に母親らしい食事」に書き換えてみました。ついでに、イラッときたり無力感に襲われたときには、とにかくまず「ま、いっか」とつぶやくようにしてみたんです。
たったそれだけですが、数日前までの「ずっと怒りの感情を抱えながら食べ物をただ口に押し込む」という状態から、「自分が食べたいものを「食べる」」という状態に変わりました。
さらに、土曜日の講座からダッシュで保育園にお迎えに行っている途中で「お熱です」の電話を受けて、猛ダッシュで保育園に駆け付け、食べられないであろう長女のためにアイスクリームなどを調達して、まだ回復しきっていないために自宅でお留守番していた次女を夫から受け取り、次女抱っこ&長女おんぶの状態で仕事に行く夫を見送り、「ごめん、何も準備できなかった」の一言で済まされた夕食の支度を次女の腹具合と長女の「頭痛い~」の訴えを気にしながら大急ぎで済ませ、とりあえず次女を食べさせて、長女を清拭して寝かせ、次女をお風呂に入れてしばらく2人の時間を確保し、長女を起こさないように次女を寝かせつけ、翌日不在の「下準備」をし・・・という状況で「ま、いっか」を呟いてみました。普通なら「何で私1人でこんなにやらなきゃいけないのよ~」となるんでしょうが、「ま、こういう日もあるよね」で済まされたので不思議です。
以前、「子育ては『楽しもう』としなくていい」という記事を書いた時、ものすごく共感しましたという感想を多数いただいたのですが、「楽しもう」とするってことは育児が「楽しくない」という前提があるんですよね。だから、育児は楽しもうとしなくていいんです。
育児は大変なんだって、そういうものなのだと思っていいのです。その「大変さ」を自分にとってどのくらい負担になるものとしてランク付けするか、「ま、いっか」程度にランク付けするか、それが「自分次第」ということなのだと今回のセッションで発見しました。
日付:2015年10月26日 カテゴリー:日々の雑記
子どもの問題は「親の意識の鏡」
先日、発達障害や情緒障害のお子さんをもつ親向けのセミナーを受けてきました。私自身は「親」としてではなく、カウンセラーとしてこの分野も薬を使わずに治療を行っていきたいと思い、勉強のために受講したのですが、カウンセラーとしてよりも一人の母親として大変勉強になりました。
セミナーの内容の詳細はご紹介できないのですが、結論だけお伝えすると、発達障害に限らず子どもの問題行動や病気は「親の意識の鏡」であるということです。このようにお伝えすると、お子さんの何らかの問題で悩んでいる方は、「何でもかんでも親が悪いって言うの?」「すでにこの子のことでこんなに悩んだり苦しんだりしているのにさらに追い打ちをかけるような責め方をしないで」と思われるかもしれません。私自身も、長女が喘息の疑いと診断された時、真っ先に自分を責めました。喘息は母親の過干渉が原因となりうることを知っていたからです。そして、代替医療のセミナーに参加した時に「喘息は母親がうるさすぎるとなるのよ」と言われて大打撃を受けましたから。実際は、長女の症状の原因は私ではなく、もっと医学の手が届かないものが原因となっていたので、それを解消したらすっかり症状はでなくなりました。
子どもの問題が親の意識の鏡=親が悪いと責めているわけではありません。なので安心してください。
ただ、子どもの症状や行動を「子どもだけ」を見て解決しようとしても難しいということに気づかなければ、例え今出ている症状が治まったとしてもまた新たな問題が出てくるのです。逆に言えば、親の意識さえ変えれば、子どもはよくなるということですから、「親に非があるのだ」と受け止めるのではなく、「解決のカギは自分が握っている」と捉えていただけたらなと思います。
私自身は、1年くらい前から「上の子かわいくない症候群」で悩んでいました。スピリチュアルなセッションを受けたり、子育てアドバイスの本を読んだり、自分に笑顔を取り戻すために大好きなミュージカルの舞台に立ったりしましたが、長女に対する私の気持ちは変わらず、また長女の問題行動はどんどんエスカレートしているように見受けられました。
特にここ数週間は、本気で長女の今後の育て方について専門家の意見を求めた方がいいのではないかと思っていたくらいなのですが・・・何があったかといいますと、6月から習い始めたバレエ教室を一時お休みしなければいけなくなったんです。表向きは「発表会までの間通常のレッスンをほとんどしなくなるのでいったん休止しませんか?(娘は発表会に申し込んでいません)」と言われたのですが、娘のあまりのお行儀の悪さに先生もお手上げ状態になったのだと思われます。1時間のレッスンのうち、ちゃんと踊るのは15分程度で、後は走り回ったり私に泣きついたリバーで鉄棒ごっこをしたり・・・やりたい放題なわけです。先生や私が注意しても聞かず、「そんなに嫌ならバレエ止めて帰ろう」と言うと「やるの~」と言ってごねるという始末。私も、さすがに申し訳なくなって、やめることを提案しようかと悩んでいた矢先の先生からのお話しでした。
レッスンのたびに娘に「バレエ続ける?」と聞いていたのですが、いつも「やる!」と答えていたんですよね。4歳の子の言うことなのでどこまで鵜呑みにしてよいのかわかりませんが、少なくとも本人がやると言っている間は続けさせようと思っていました。でもその日は、あっさり「もうやめる」と言うので、そのままひとまずお休みすることにしたんです。
先生の方からこういったことを提案されたことは、親として少なからずショックで、そのせいでしばらく悶々としていました。なぜこんなに自分がモヤモヤするのかを色々考えてみたら、「自分からやると言い出したことを継続できなかった」「教室から問題児扱いされた」「今後小学校に上がってもきっと度々先生から呼び出されるような子になるだろう」といった思いが湧き上がってきました。娘が例え教室をウロウロして注意されようが、学校に行かないと言ってごねようが、すべて受け入れて好きにさせようと思っていましたが、いざそうなるとやっぱり自分の中にある「こうすべき」「こうあるべき」という規範意識が対抗しようとするのだなと感じたのです。
結局、バレエ教室をお休みすることにして、代わりに同じ時間帯に保育園でやっている体操教室を受けさせてみたら、なんと1時間の教室をほぼきちんと受けて先生のいうことも聞いて、おまけに周りの男の子たちに負けない運動神経を発揮していました。バレエは本人が言っているほど好きではなかったんだな、と気づいたわけですが、お休みすると決めた後も毎週のように「またバレエに行きたい」と本人は言うのです。私も4歳の時にバレエの魅力にはまって、5歳から習い始めたのでわかりますが、好きだったらあんなレッスン態度にはなりません。娘の「バレエをやりたい」の背景にある本当の意図は何なのか探ってみたら「早くお迎えに来てほしい」でした。
バレエ教室に行くために、いつもは18時お迎えのところを15時にお迎えに行っていたんですよね。しかも、長女だけ早くお迎えで次女はバレエ教室が終わるまで保育園です。長女はその「早お迎え」が欲しかったんだと思います。
バレエ教室の件は、長女の問題行動のごく一部なわけですが、こういった行動を長女がとる原因を「私の中に」探してみたところ、1つは自分の中にある「規範意識」を長女が壊してくれているのだということに気づきました。そして、もう1つ大きな原因がありました。それは、私自身が長女に「問題児」になってほしいと無意識のうちに想っていたのです。
もちろん潜在意識でですから、私が顕在意識で長女を問題児扱いしているわけではありません。でも、潜在意識は長女に問題を起こしてほしいと願っていたのです。だから、その願いは次々に叶えられていたんですね。
なぜ私が長女を「問題児扱い」したがっていたのか・・・それは、夫へのメッセージでした。
一般的に、子どもを病気にしたり問題児にしたりする母親の意識の背景として、「手のかかる子にすることで自分の『母親としての役割』をより強めたい」「自分が『母親として』必要とされる状況を生みだしたい」という意識が働くことが多いのですが、私自身は娘に必要とされなくてもすでにやりたいことがしっかりあって自分の存在意義も娘とは切り離されているので、自分の価値証明と娘の存在はリンクしません。なので、このケースには当てはまりません。
私の場合は、長女が問題行動を起こせば、少しは夫が長女の育児
の大変さを分かってくれるだろうと思っていたのです。なぜそんなアピールが必要になったのか、それは、夫の口癖が「彩ちゃんは本当に手のかからない育てやすい子だね」だったからです。1時間おきの夜泣きで憔悴しきっていたことや、ミルク拒否のために働きながら完全母乳で頑張るしかなかったことや、離乳食をほとんど食べてくれずに苦労したことなどは夫からは見えておらず、「私がどれだけ大変な思いをしてきたかあんたはちっともわかってないでしょ~!」ということが言いたかったわけです。育児の「いいとこどり」をして、いつものんきに娘たちをただただ「かわいいね~」と言っている夫のことがうらやましくもあり、腹立たしくもあったんですね。
今の状態で長女が問題を起こせば、さすがに夫にも「見える」形となるので、私は一生懸命長女を問題児に仕立て上げようとしていたようです。
私の中の「原因」が分かれば、対処法は簡単です。長女が問題児になる必要がなくなればよいわけですから、夫に私の感じていることを伝えればよいわけです。ついでに、夫に私の苦労を「認めて欲しい」と思ってしまうのは、私が自分で自分がやってきたことを認めたり褒めたりしてあげていないせいなので、自分で自分をしっかり褒めました。
他人から褒めて欲しいと思っている時は、自分が自分を認めてあげていないことが多いんです。内側からの「承認」がないから、外野からそれを欲しがってしまうんですね。自分で自分をしっかり褒めたあげたら、夫が私の苦労を知ろうが知るまいが、それはどうでもよくなってきました。縁の下の力持ちのおかげでニコニコしていられるあなたは幸せモンだわね~、と思えるようになるわけです。まあ、それでも、この一連の関連性は一度は話しておきたいんですけれどね。
日付:2015年10月22日 カテゴリー:日々の雑記
どのように健康を目指すかは「自分」で決めること
がんの治療法や予防法について様々な意見を見るにつけ、極端な自然療法派の方の発信に何とも言えない違和感を感じていました。その違和感をクリアにしてくれる、とてもスマートでまとまった記事があったのでご紹介させてくださいませ。
「私からのお願い」
私は西洋医学を学んだ医者ですが、自然療法を選択したいという方がいらしたらその選択をサポートしますし、「薬」以外の方法で治療したいと言われたら自分自身が試してこれならお勧めできるという代替医療をご紹介することもあります。でも、自然療法を「推奨」しているわけではありません。西洋医学を「否定」しているわけでもありません。
私にとって、抗がん剤と金の延べ棒のどちらが優れているのかということは重要ではないのです。もちろん、明らかにまがい物で、人の弱みに付け込んだような代替医療もどきがあったら、はっきりとそれはやめるようにお伝えしますが。基本的に、何かを否定している限り病気を作り出す根源はなくならないと感じています。
私が大切にしているのは、目の前にいらっしゃる患者様にご本人にとっての「ベスト」は何かのかを一緒に考えるということです。一般の方の知識だけでは何が「ベスト」なのかよくわからない、という場合に標準的な治療やご本人を拝見しての印象をふまえて「こうしたらいかがですか?」とご提案します。
様々な代替医療を学んだり自分で試したり(自分の体で実験しています・・・)しているのは、いらっしゃる方にとって何が「ベスト」なのかがふたを開けてみなければわからないからです。できるだけ提案できる手持ちのカードが多い方が対応できるから、漢方もアロマもキネシオロジーもカウンセリングも学ぶのです。
自分にとって良いと思われるものが他の人にとっても同じ効果が得られるとは限りません。なので、標準的治療以外の方法を選択した人や、検診は受けない・ワクチンは受けないという選択をした人がそれを体験談として語ることはよくても、その選択を他の人に押し付けてはいけないのです。
これは、自宅分娩をした人が他の人にそれを勧めてはいけないのと同じです。私は自宅分娩をした人に「何でそんな危険なことをしたんだ!」なんてことは言いません。「素敵な体験ができてよかったですね」といいます。無事に産まれた後ですから。でも、自分自身はどんなに勧められても自宅分娩は選択しません。
薬に使い方や治療法の選択や予防の方法も、人によって何が必要なのか、何が害なのかは異なります。抗がん剤だって、それが命をつないでくれることもあれば、命を縮めることもあります。一概に、すべての化学療法が「毒」だとは言えないのです。
先日の記事にも書きましたが、手術をしないという選択をした人が手術をするという選択をした人に対して言及してはいけないのです。特に、それを医療関係者の方が気を使って発信することは避けるべきだと感じています。
がんもその他の病気も、きちんと生活や食事を改善して、予防に努めていれば「検診なんて受けなくても大丈夫」といえるのかもしれません。でも、「病気にならない生活&思想」ができている人は、とてもとても少ないと感じています。
私自身も、どうすればいいのかは分かっていてもそれが実践できないことは多々あります。例えば、40度のお湯で30分以上しっかり温まった方が健康のためにはよい、と言われてもお湯につかってわずか3分で娘が起きてきて慌てて添い寝に戻ってやらないといけないことだってあるわけです。自分の免疫力を高めれば、ワクチンなんて必要ないと、と言われるかもしれませんが、妊娠中も授乳中も自分で自分の体が守り切れないほどの状態になるわけです。
どのような治療を選択するのか、どのような予防法を選択するのかは、結局「どのように生きたいのか」につながると思います。
川島なお美さんのように、積極的な治療を選択せずに生きている時間は短くなっても最後まで「女優」でいる、というのも素敵な生き方だと思います。逆に、一日でも長く生きられるように受けられる治療はしっかり受けるというのも、勇気ある選択だと思います。
もし私が独り身だったら、もしかしたら積極的な治療は行わないかもしれません。でも、2人の娘がいる今の状態だと、どんなことをしてでも娘たちが大きくなるまでは生きていようとするでしょう。できるだけ入院は避けながら、通院で受けられる治療を選択して、代替医療でそのダメージを緩和するという形をとるかもしれません。
どのような治療法も予防法も、それを否定するということは、その選択をしている人の「生き方」を否定することになります。だから、私は、そういった発信に対して常に違和感を感じてしまうのです。
どうか、どのような選択をした人も自分の「健康に戻る力」を信じて、自分の選択を受け入れて欲しいなと思います。
日付:2015年10月8日 カテゴリー:日々の雑記
マンモグラフィーで乳がんのリスクは上がるのか?
以前からマンモグラフィーの被ばく線量に関してはご質問を頂くこともありましたが、最近やたらと「マンモグラフィーによる被ばくが乳がんの原因になる」といった記事が目につくようになってきました。
私自身は婦人科の専門ですから、婦人科の検診として何の検診がどの程度有効であるかは、医学的知識としても、そしていらっしゃる患者様を拝見して感じることからも、確信をもってご説明できます。
マンモグラフィーに関しては乳腺外科の専門になりますので、私自身がマンモグラフィーの検査を行ったりその結果をご説明することはありません。なので、マンモグラフィーの被ばく線量については、一般的な医学的考察からそのリスクを考えることしかできませんが、結論から言うとマンモグラフィーの被ばく線量はがんの原因になるほど高いものではありません。
マンモグラフィーの有効性とリスクについてはこちらの記事http://www.jbcsftguideline.jp/category/cq/index/cqid/500001がよくまとまっていますので、こ難しい説明や「エビデンス」がお好きな方は、この解説を参考にしていただくとよいと思います。
マンモグラフィーの被ばく線量が他のレントゲン検査に比べて高いように思われているようですが、実際は胸のレントゲン検査による被ばく線量をさほど変わりません。なぜ被ばく線量が下げられるのかというと、マンモグラフィーでは強く乳房を圧迫することによって、できるだけ乳腺を薄くして低い線量で済むようにしているからです。
実際、マンモグラフィーによる被ばく線量がどのくらいかを数値に表すと、実効線量が0.05~0.15mSvになります。人が普通に日常生活を送っていても、自然界からある程度の放射線を浴びますが、それが年間約2.4mSvなのです。つまり、例え1年間に10回マンモグラフィーをとっても、自然に浴びる放射線量より少ないということです。ちなみに、飛行機に乗ると被ばく線量は上がるのですが、東京~サンフランシスコを飛行機で移動した場合の自然被ばく線量は約0.038mSvと言われています。もし、マンモグラフィーで乳がんになるのだとしたら、国際線の客室乗務員の方の乳がんリスクはどうなるでしょう?
ではマンモグラフィーは全く乳がんのリスクにならないのかというと、リスクが「ゼロ」とは言えません。それは、被爆による「確定的影響」と「確率的影響」というものがあるからです。確定的影響は、ある一定の線量を超えるとがんのリスクが高くなりますよ、というものです。これは組織(臓器)によってどのくらいの線量を超えると危険なのかが決まっていまして、マンモグラフィーの場合、例え毎年マンモグラフィーをとっても乳腺の「ここが危険」というラインは超えません。つまり確定的影響はないと言えます。
一方、確率的影響はどのレベルでリスクが上がるかといった線引きがありません。もしかしたら、たった1回のマンモグラフィーが乳がんを発生しさせてしまうかもしれないというものです。この確率は「ゼロではない」としか言いようがありません。例えば、乳がんになりやすい遺伝子を持った肥満で乳製品が大好きで妊娠・出産経験がない女性がマンモグラフィーを受けた後に乳がんを発症した場合、もしかしたらマンモグラフィーのせいで乳がんができたのかもしれないけれどその他のリスク要因もあるから断言はできない、ということになります。
では、全員がマンモグラフィーを受けた方がいいのかというとそうではありません。少なくとも、30歳以下の人はマンモグラフィーを受けるメリットがそれほど高くはない又はデメリットが上回る可能性があるので、乳がん検診を受ける場合は超音波検査を受けた方がよいといえます。30代前半についても、マンモグラフィーより超音波検査の方がよいでしょう。
逆に40歳以上の方については、マンモグラフィーによる検診が有効といえます。ただし、乳腺の密度が高い方はマンモグラフィーだけでは見落としのリスクがありますので、超音波検査との併用検診が勧められます。マンモグラフィーと超音波検査は、お互いの「発見しにくい異常」を補い合える特性がありますので、一緒に受けることで精度は上がります。
検診を受けるデメリットの1つとして、過剰に異常をひっかけてしまうというものがあります。確かに、検診で「もしかしたら乳がんかもしれないから精密検査を受けて下さい」と言われて、細胞診などの詳しい検査を受けたらなんでもなかった、というケースはしばしば見受けられます。
検診は、できるだけ見落とさないように小さな異常も「疑いあり」に入れるため、このようなことが起こりうるのです。本当に乳がんの人だけをピックアップするように異常と判定する境界線を下げると、見落としが増えるということになります。検診の目的を考えると、ある程度過剰に異常が出てしまうのはやむを得ない部分があります。
毎年検診を受けていれば、前の検査結果との比較ができますから、この過剰に異常を指摘されるということが少なくはなってきます。
乳がん検診も子宮がん検診も、受けるデメリットより受けないデメリットが大きいことは、とても進行したがんを拝見するたびに痛感します。検診は、適切な方法で受ければやはり有効性の方が高いのです。
ただし、検診を受けるよりもっと大切なことがあります。それは、「がんにならない習慣」を身に着けることです。がんになる人は、必ずその原因となる行動・食生活・思考のパターンがあります。それを変えずして、がんを恐れて不安な中で検診を受けても、がんを防ぐことはできないのです。
日付:2015年10月3日 カテゴリー:日々の雑記
がんは手術しなくても消えるのか?
ここのところ、川島なお美さんと北斗晶さんの報道を受けてがんについての話題がネットでも多く見受けられます。中には、「がんは切ってはいけない」「抗がん剤は毒でしかない」「体を温めればがんは治る」といった極論も多く、医者の中では比較的自然療法派の私でさえ、「それは違うでしょう」といいたくなる記事も多く目につきます。
まず最初に言っておきたいのは、西洋医学的に「手術・化学療法・放射線療法」ががんの3大療法であることは基本中の基本で、これらの治療を今現在受けている方が、ネット上の自然療法派の方の意見を見てご自身が選択なさった治療法に対して否定的な考えを持つことだけはしないでいただきたい、ということです。不安な気持ちで治療を受ければ、治療効果も下がってしまいます。
極論の中には、病院が儲けるために必要ない人にまで抗がん剤を使っている、という記事もありますが、高いお薬を使ったからと言って病院が儲かるわけではありません。お薬の値段は保険点数で決まっていますから、患者様の負担が大きい薬は仕入れ値も高いのです。
もちろん、世の中には良心的な医師ばかりではないことは分かっていますし、自分でも「もうこの医師にはかかりたくない」という医師に遭遇したこともありますから、医師が全員絶対に患者様のためだけを思って患者様にとってのベストを考えて治療計画を立てているとは言い切れないかもしれません。でも、多くの医師は少なくとも「スタンダードな治療」を提案しているはずです。各病気には、基本的な治療方針について「ガイドライン」というものがありますから、通常はそれにのっとって治療を行っていくのです。本当は必要ないかもしれない治療が行われている可能性については、また別の機会にお話しできたらと思います。
がんが見つかったら、まず最初に手術を勧められることがほとんどです。これは、がんだと思われる部分が本当に「がん」なのかを確定する方法は、唯一その部分を切り取ってきて顕微鏡で組織を見てみることだからです。手術をしなくても、がんかどうかの確定まではできるケースもあります。例えば、子宮頸がんは子宮の出口にできるがんなので、お腹をあけなくても膣の方から病気がある部分を切り取ることができます。通常は「ここが一番怪しい」という部分を少しだけ切り取る「組織診」で、がんなのかどうかを診断することができます。一方、卵巣がんは腫れている卵巣そのものをとるまではそれが「がん」なのかおそらくがんの手前の「境界悪性」なのか「がんに見えたけど良性」なのかを判別することはできません。
手術を行う目的は、がんの種類と進行具合によって多少異なりますが、多くの場合は、例え術前に「がん」だと確定できても、それがどの範囲まで広がっているのか、どういう特性を持った組織なのかを見るために、そして、できれば悪い部分を全部取り除いてしまうために行うのです。
がんは手術なんてしなくても消えるものだ、という意見もあるかと思います。これに対して私の個人的な意見は、「消える人もいれば消せない人もいる」ということです。がんの原因となる悪習慣をすべて改め、思考も改善し、なぜこのタイミングでがんになったのかをきちんと理解できた人は、もしかしたら手術をしなくてもがんが消えてくれるかもしれません。でも、それができる人はごくわずかだと感じています。例え生活習慣は変えられても、思考のパターンがそのままだったり、がんになることで学ぶべきことが受け取り切れないケースが多いように見受けられるのです。そのような人が、がんを「切らずに治す」とがんばって手術で切り取りきれるレベルだったものをむやみに進行させてしまうことはとても危険だと思います。
時々、「子宮頸がんのステージ3が様子を見ているうちに消えた」という体験談が出てきます。問診でそのように書いてくださる方もいらっしゃいます。よくよくお話を伺うと、「ステージ3」ではなくて、子宮頸がんの細胞診の結果が「クラス3」だったのが正常になったということのようです。おそらく「子宮頸がんが勝手に治った」という体験談の大部分は、この「クラス3」つまり異形成という状態から正常化したというものなのだと思われます。異形成はほっておいても正常化することが多いわけですから、「がんが自然に治る」のと勘違いしてしまっては危険です。
がんになったら絶対に手術しなければいけないというわけではありません。がんのある場所、進行具合、ご本人の年齢や全身状態によっては、手術をすること自体が生命予後を悪くするということもありうるでしょう。
一方で、子宮頸がんの初期など、早く見つけて適切な範囲をきちんと手術で取り除けば、それ以上の治療は全く必要なく完治できるものもあるということを理解しておく必要もあります。
手術を受けないデメリットについてきちんと理解して、手術をしないという選択をすることは間違いではありません。最も大事なことは、手術をしないという選択をした人が、手術をするという選択をした人に対してそれを否定してはいけないということだと思います。
日付:2015年10月1日 カテゴリー:日々の雑記
がんで死なないために最も重要なことは?
川島なお美さんの死や、北斗晶さんの乳がん手術の報道を受けて、がん治療についての様々な意見が飛び交っていますが、中には医療者から見ると明らかに間違っている内容や、今現在がんの治療を受けている方を混乱させてしまうような内容もあって、読めばよむほどモヤッとしてしまいます。
私がまだ研修医の頃、がんセンターに勤務していた時に担当させていただいていた卵巣がんの再発患者さんが教えてくださったことが、とても印象的でした。
「せんせ~、がんで死なないために一番重要なことって分かる?『いつ』『誰に』がんを発見してもらうかってことだよ」
その方は、がんの自助グループにも入っていらして、多くのがん患者さんと接する中で出てきた意見なのだと思います。その時も、今思い返しても、もっともな意見だと思うのです。
「いつ」発見されるか、つまりがんのごく初期の段階で発見できるか、手術もできない程進行した段階で見つかるかによって「予後」つまりどのくらいそのがんが「治せるか」またはどのくらい「生きられるか」は決まってしまうと言っても過言ではありません。
ある意味、誰が手術しても取切れるくらい初期の初期で見つかれば、がんで命を落とすリスクはほとんどないわけですし、逆に全身に転移しているような状態で見つかれば、その先化学療法を選択しようが自然療法を選択しようが生命予後にほとんど差は出ないわけです。
ちなみに、私の父親は食道がんの4期、つまり全身に転移してすでに「末期」といえる状態でがんが発見されました。自覚症状があったにもかかわらず、本人が半年以上放置していたのです。もちろん、定期検診なんて受けていませんでした。
発見された段階で、どのような治療を選択しても父親の生命予後はあまり変わらないだろうと分かりましたから、家族の立場としては「できる限り口から摂取可能な状態を保つこと」「わずかな可能性にかけて負担が大きい治療を行うよりも除痛を中心とした治療を行うこと」を希望しました。ただ、本人が何をどう説明しても(「身辺整理をし始めてください」と言われても)、がんは「治る」と思っていたため、化学療法を行うことを希望してしまったんですが・・・結局、全身状態が悪すぎて、化学療法は1回しか行えず、発見から8か月後にこの世を去りました。
「誰に」発見してもらうか、これは、がんを疑った段階で適切な検査や治療に導ける医師に出会えるか、そして、がんの状態に応じて最も有効な治療を選択できる医師に出会えるか、ということです。
川島なお美さんが、がんが発見されてから手術を受けるまでに半年も時間をかけてしまったことは、生命予後を悪くしてしまった一因と言わざるを得ません。もし、確定診断のためにもすぐに手術を受けた方がよいということを熱心に説明してもらっていたら、少しは早く有効な治療を受けられたかもしれませんが、どんな医師に出会っても本人が「納得がいくまで説明を求める」というスタンスでセカンドオピニオンを求めてドクターショッピングをしてしまっては、結果は同じだったのかもしれません。
大事なことは、治療を開始する時期を遅らせてしまわないこと、治療の有効性と体への負担のどちらが「より大きいのか」をきちんと見極めることです。そして、それらを一般の方が自分の知識だけで行おうとしても、なかなか難しいということを知っておかなければいけないと思います。
がんの治療を選択する上で、いわゆる西洋医学的な治療を何も受けないという選択も、本人が納得した上での選択であれば、大事な選択肢だと考えています。「どの治療法を選ぶか」も含めて、それがその人の「寿命」なのだと思うのです。例え生命予後が悪くなっても、抗がん剤は使いたくないと本人が考えていれば、その選択は本人にとって「正解」です。
ただ、その選択をする上で「選考にする情報」が間違っていては危険です。今後、ネット上に流れている情報の中でいくつか気になったものをピックアップしていきたいと思います。
日付:2015年9月27日 カテゴリー:日々の雑記
5周年・ありがとうございます
9月11日はクリニックの開院記念日でした。なんと、あっという間の5周年!です。
と言っても、日々の診療と子育てでバタバタ~っとその日は過ぎ去ってしまったのですが・・・むしろ、「いつもと変わらない1日」をその日も淡々と積み重ねられたことに、心から感謝したいと思います。
開業した時もそうだったんですが、その日が来るのが「よい意味で」特別なことではなく、まるでそうなることがあらかじめ分かっていたかのようにものすごく穏やかにその日を迎えていたんですよね。開業する前は、開業時は「とうとうこの日がやってきたぞ~!」的なものすごい感動があるのかと思っていたのですが、10年以上温め続けてきた夢が実現したという割には、本当にものすごく「自然」だったんです。以前からそこが自分の居場所だったように、しっくりしていて、そしてじわ~っと温かい幸せを感じていました。
5周年を迎えた時も、やっぱり同じような感覚でした。何かをやり遂げた感じとか、目標を「達成した」という感覚ではなく、ちょっと言葉にするのが難しいのですが、ちょうど、朝起きて「あ、今日も生きている、ありがとう」という感じに似ている気がします。
もちろん、5年間の間に2回の出産があったわけですから、それなりの心痛も苦労もあったわけですが、振り返ってみると「あ~、ありがたいな~」の一言でまるっとしめてしまえるから不思議です。
特に、1人目の妊娠は、開業する段階で分かっていたので、開業してわずか半年でクリニックを留守にしなければいけないということにはとても大きな不安がありました。ギリギリまで代診の医師が確保できず、そうこうするうちに予定日は近づいてくるし、このまま誰も見つからなかったらどうしよう~と、悩んでいた日が懐かしく思えます。
結局、「出産の日まで代診の先生が確保できなかったら、出産の前日までは頑張って、できるだけ早く復帰しよう。1~2週間の急な休診で患者様には迷惑をかけてしまうけれど、自分がなぜこのタイミングで妊娠を目指したのかをきちんと説明してお詫びをすればよいのだから、それで理解が得られなければ仕方がない」と腹をくくったんですが・・・腹をくくったら、今もお手伝いしてくださっている浜田先生とのご縁がつながりました。
まあ、本当に産む8時間前まで診療をして、退院してすぐに復帰するとは、誰も予想はしていなかったと思います。偶然にも2人目も診療を終えた翌日に産まれているんですが、どちらも陣痛促進剤は使っていないんですよ。自然な陣痛が、ベストタイミングで来てくれたんです。空気を読んで生まれてきた娘たちには、本当に感謝感謝です。
まだまだやりたいことが多すぎて、子育てとの時間配分にヤキモキしたりしていますが、これからもより多くの女性のサポートをさせていただけるように、クリニックとともに成長していきたいと思います。
よかったら、これからも応援してくださいませ。
日付:2015年9月16日 カテゴリー:日々の雑記
脳内独り言の影響力
昨日は、以前からずっと受けたかった杏奈先生のプライベートレッスンを、やっとやっと受けてきました。フランクリンメソッドについて知りたかったので、メソッドについての基本的な考え方や簡単なムーブメントで体の使い方を教えて頂きました。
中でも、一番興味深かったのが、イメジェリーやメタファーを使って身体機能を向上させるという視点です。簡単に言うと、脳がどの様な言葉を思い浮かべるかによって身体機能が変化するというものです。
レッスンでは、即興の腕の動きを「ネガティブな言葉を心の中で呟きながら」行った後に、「ポジティブな言葉を心の中で呟きながら」やってみました。言葉を口にしていないのに、端から見ていても、その動きをどの様な言葉を思い浮かべながら行っているか分かるんです。自分の体感も、もちろん全く異なります。
分かりにくい~と思った方は、片手でギリギリ持ち上がるくらいの重さの物を、「ついてない、バカ野郎、重い~」と言いながら持ち上げてみてください。その後に、「ついてる、ありがとう、軽い~」と言いながら持ち上げてみてください。重さが変わったはずです。
体の機能をコントロールしているのは、脳です。脳がどの様な信号を出しているのか、一番分かりやすいのが発している「言葉」だと思います。実際に口にしている言葉はもちろんですし、口に出していない「脳内独り言」も同じ影響があります。
この、脳内独り言、人は1日で何と2万回くらい語りかけているそうです。その言葉がネガティブな言葉ばかりだったら、体にどの様な反応が現れるか…想像できますよね?
ちなみに、口にしている言葉も、脳内独り言も、脳は「主語を見分けられない」という特性があります。つまり、他者に対して向けたネガティブな言葉を、主語を自分に置き換えて理解してしまうのです。逆もしかりなので、他者に対して誉め言葉や感謝の気持ちなどを常に発信していると、自分がそれらを受けとることになります。
脳内独り言は、ちょっと意識するだけで変えられます。無意識に、ネガティブな言葉を連発してしまったら、最後に「っていうのは嘘~」と笑い飛ばすとよいのだそうです。
自分の体は、自分がコントロールできる…それを、体感させていただいたレッスンでした。
日付:2015年8月15日 カテゴリー:日々の雑記