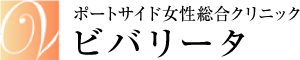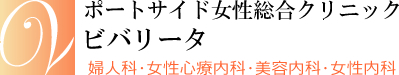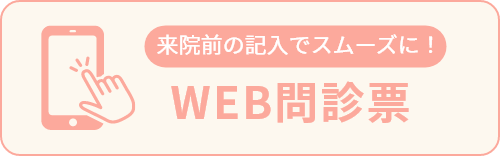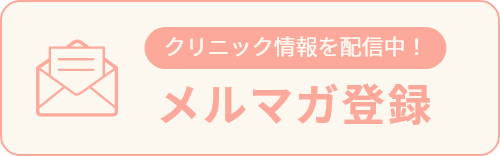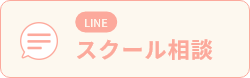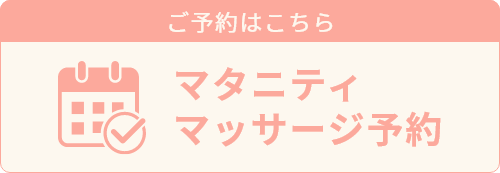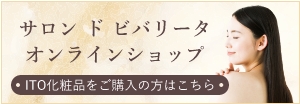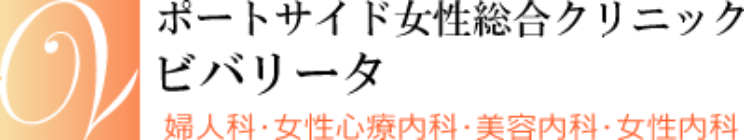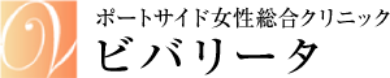日々の雑記
ゴールのその先が見えていますか?
皆さんは達成したい目標がある時、どのようにそれを設定しますか?
受験生だったら「○○学校に合格したい」、社会人だったら「年収〇円になりたい」「○○の資格を取得したい」、妊活中の方だったら「妊娠したい」という感じでしょうか?
実は、この「ゴールの設定の仕方」が間違っていると、なかなかゴールできなかったり、ゴールの手前でウロウロしてしまったりするのです。
私が大学6年生の時、要するに国家試験の受験勉強をしている時ですね、ミュージカルに夢中になっていました。だから、「国家試験に合格したら女性をサポートする医者になろう(今の私がやっていることですね)、国家試験に落ちたらNYに行って舞台の勉強をして啓発的な内容を含んだ作品を作る人になろう」と思っていました。
そう、国家試験に合格するかどうかは私にとってゴールでもなければ、重要事項でもなく、単なる「通過点」だったのです。道が二つに分かれていて、そのどちらに進んでもまた新たなゴールがあり、そしてその先にやりたいことがある、といった状態です。
ちょっとイメージしてみてください。100メートル競走をする時に、ゴールに壁が立っていて、「ここがゴールです!!」と張り紙がしてあったら、そのゴールを全速力で駆け抜けることはできるでしょうか?じゃあ、壁ではなく取っ手のついたドアだったらどうでしょうか?ガラスでできた自動ドアだったらどうですか?
では、白いテープのさらに100メートルくらい先に、大好きな人たちが「頑張って~」と応援の旗を振っていたらどうですか?どれが一番「全速力でゴールを駆け抜ける」ことができそうですか?
もうお分かりですよね?ゴールを設定する時には、そのゴールの先が見えているかどうかが、達成できるかどうかのカギになるのです。
受験生だったら、その学校に行って何がしたいのか、何を学んで何を身に着けて卒業後にそれらをどう活用していきたいのか、まで考えて受験勉強をする。単純にその学校に「合格したい」では、合格の一歩手前で失速してしまう可能性があります。場合によっては、ずっと「合格する」ことが目標になって受験を繰り返してしまうことになりかねません。
現在受験勉強真っ最中で「そんな先のことまで考える余裕なんてないよ!」という人は、いえ、そういう人こそ、やってみてください。入りたい学校の校門で「合格しました」と「卒業しました」の写真を撮ります。そして、合格した自分から合格した秘訣を聞き出します。さらに、卒業した自分からどのようなキャンパスライフを送ってこれから何をしようとしているのかを聞き出します。難しい参考書とにらめっこするよりも、よほど効果的です。
日付:2018年7月30日 カテゴリー:日々の雑記
ファボワール供給再開のお知らせ
長期安定性の件で、メーカーさんが自主回収の措置をとっていましたファボワールですが、有効期限を3年から2年に変更する形で再供給されることとなりました。
当院でも、7月27日午後からファボワールの処方を再開させていただきます。
自主回収後にご不便をおかけした患者様には申し訳ございませんでした。
本日午後から通常通りの処方が可能ですので、現在ファボワールを服用中の患者様は予定通り欠薬前に受診していただければ大丈夫です。
日付:2018年7月27日 カテゴリー:日々の雑記
「自由」とは「○○な感覚を持って生きていること」
最近、診療の中でも、その人が持っている言葉の定義やその裏にある意図を意識して伺うようにしています。
例えば、ある方は「普通」になることが一番重要だとおっしゃっていました。「あなたにとって『普通』とはどういう状態ですか?」と確認すると「平均的であること」「周りと同じであること」「浮いていないこと」といった、その方の定義が出てきました。この方の場合、「外的基準」と言って、周りの目を気にして行動や選択してしまう癖がとても強く、自分がどうありたいか・何をしたいかよりも「周りから変な目で見られないか」の方を気にして生きていらしたのです。
でも、その人の本来の姿はとても個性的で独創的なアイデアをたくさん持っている方でした。「普通」であろうとすればするほど、本来の自分の姿からは遠のいてしまうので苦しくなってしまいます。この場合は「普通」の定義を「自分基準」で書き直せばよいのです。
そもそも、今「普通」だと思っていることは何が決めた「普通」なのか。例えば、日本では一夫一妻制が「普通」ですが、海外には一人の男性が4人の妻を持つことが「普通」である国もあります。その国の男性から日本男性を見たら「たったひとりの女性しか養えないのか。ふがいない奴だな~」と言うことになるかもしれません。
こういった言葉の定義や、その人が持っている背景は、住んでいるエリアやそこにある「文化」とも密接にかかわっていたりします。
このような言葉の「定義」が、自分が欲しい結果に対してずれていると、いつまでたっても欲しい変化が手に入らなかったりします。なんせ、そもそもの大前提がずれているわけですから、ゴールにたどり着けるわけがないのです。
そのずれを大きく感じる言葉一つが「自由」というものです。よく「自由になりたい」「自由が欲しい」「自由な身分になりたい」と言ったりしますよね。皆さんにとって「自由」とはどのような状態のことを指しますか?ちょっと、自分が持っている自由の定義を考えてみてください。
多くの場合、自由とは「制限がない状態」「束縛がない状態」をイメージしてしまいがちです。実は、この定義で自由を求めていても、真の自由な状態にはたどり着けません。なぜなら、「自由になりたい」と思っている時、頭の中には「制限された不自由な自分」がイメージされるからです。制限された状態をイメージしながらその制限を外そうと頑張ってしまうと、脳は混乱してフリーズしようとします。
自由を追い求めれば追い求めるほど「不自由」になっていくのです。
では、そもそも自由とはどのような状態を指すのでしょうか?本来の自由とは、手に入れようとしたり追い求めるものではないのです。自由とは、ある感覚を持ちながら生きることを意味します。そして、その感覚を持っておくためには『多様性を受け入れる』ことが非常に重要になってきます。
例えば、私は今女性の風貌で女性として生きていますが、それは「女性のまま生きてもいいし、男性の風貌で中身女性で生きてもいいし、役割だけ男性の役割をしてもいいし、心身ともに男性になってもいいし…」という中で、今のスタイルを選択しているにすぎません。誰かから何かを押し付けられてもいないし、複数の選択肢から自分に合っているものをただ選んでいるにすぎません。
これが脳が喜ぶ「自由」の定義なのです。
あなたの「自由」の定義はずれていませんか?
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
日付:2018年7月12日 カテゴリー:日々の雑記
過去をすべて「最適なもの」にする方法
あなたは、「過去は変えられない」「過去に起きたことはどうにもできない」と考えていませんか?患者様の中にも、過去は変えることができないのだから、「忘れるしかない」「時間が解決してくれるのを待つしかない」「一生抱えていくしかない」と勘違いしている方が結構いらっしゃいます。
「どうしようもないなら忘れてしまえ」と無理矢理忘れようとしたり、忘れた振りをしたり、もう気にしてない振りをすることもあるかもしれません。これらの対処法は、全て病気の原因になります。いくら臭いものに蓋をしても、「臭いもの」である限り臭いは消えないのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
過去の記憶を処理する方法はいくつかありますので、本気で何とかしたいと感じる方はカウンセリングセッションを受けることをお勧めします。
ここでは、自分で簡単に過去の経験や選択を「最適なものだった」ことにできる方法をご紹介します。
実はこの方法を、心理学やカウンセリングを深く学ぶ前から、患者様に使っていました。
それは、患者様が妊娠の継続を迷った時です。
私は患者様に、こうお話ししていました。
「あなたが、今、後悔しないような選択をしようと色々考えているのだとしたら、それは不可能です。なぜなら人は『今現在幸せでない』『うまくいっていると感じられていない』時に、過去を振り返って『あの時別の選択をしていれば違う結果になったかもしれない』と思うものだからです。未来のあなたが幸せを感じていなければ、今どの様な選択をしても後悔することになると思います。未来に後悔しない選択を今行うことはできません。今行った選択を『後悔のないもの』に未来の自分がすることしかできないのです」
もうお気づきでしょうが、過去を「蓋をしておきたいもの」にするのか「意味のあるもの」にするのか「感謝したいもの」にするのか、それは未来の自分が選択するものなのです。そして、過去をすべて「あの時最適な経験をした」ことにするためには、未来の自分がどのようになっていたらよいのか、そしてその未来につなげる「今」の自分がどのように行動して行けばよいのかを考えればいいのです。
過去を変えるのは案外簡単です。過去に対する「レッテル」を貼っているのは誰なのか、よく考えてみてください。それを剥がすのも、張り替えるのも、上から新しく貼っていくのも、すべては今の、そして未来の自分の手にゆだねられているのです。
あなたは過去を「忘れたいもの」にしておきますか?「感謝しかない」ものにしてみますか?
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
日付:2018年7月12日 カテゴリー:日々の雑記
「あたしおかあさんだから」?それとも「おかあさんだけど」?
作家ののぶみさんが作詞した「あたしおかあさんだから」の歌詞が話題になっているようですね。
ご自身は「お母さんの応援歌」とおっしゃっているようですが、母親という立場の私が読んでもとても違和感のある歌詞です。少なくとも「応援されている」とはとても感じられません。
いろいろ意見はあると思いますが、この歌詞のどこが「違和感」なのかは、こうすればすぐにわかります。「おかあさんだから」の部分を「おとうさんだから」に変えてみるのです。
例えば、
あたし おかあさんだから ぼく おとうさんだから
大好きなおかずあげるの 大好きなおかずあげるんだ
あたし おかあさんだから ぼく おとうさんだから
新幹線の名前覚えるの プリキュアの種類全部覚えるんだ
あたし おかあさんだから ぼく おとうさんだから
あたしよりあなたの事ばかり ぼくよりあなたの事ばかり
何が変なのか、わかりますよね?
私も爪は短いですし、朝5時起きですし、子どものことが優先になることもありますが、爪が短いのは仕事上長
いと邪魔だからですし、5時に起きるのはやりたい仕事があるからですし、子どもを優先するのは「その時の自分にとっての優先順位がそうだから」です。すべて、「おかあさんだから」ではありません。
逆に、おかあさん「だけど」子どもをシッターさんにあずけて仕事に行ったりダンスに行ったりしますし、おかあさん「だけど」子どもの遊びに付き合わないことだってありますし、おかあさん「だけど」自分の時間を満喫しています。
実際、お母さん「だから」なのか、おかあさん「だけど」なのかは、重要ではないのです。母親本人が、「私はこうしたい」と思って、おかあさん「だから」を実践しているのであれば、それは本人の基準ですからどんどんやったらよいでしょう。おかあさん「だけど」やりたいことがあったら、我慢せずにやったらよいでしょう。
この歌は、こうした「どう生きたい」という部分を、ステレオタイプな「母親はこうあるべき」という姿を押し付けているから不快に感じるのだと思います。おかあさん「だから」というより、おかあさん「なのに」こうしていないということを批判してしまうことにもなりかねません。
あなたは「だから」で生きたいですか?「だけど」で生きたいですか?
どちらも選択権はあなたの手にあるのです。「母親はこうあるべき」に惑わされず、「こういう母親になりたい」もっと言えば、母親かどうかは関係なく「こういう生き方をしたい」を実践することが、自分基準で生きることにつながります。
自分基準で生きることと、子どもをないがしろにすることはイコールではないのです。この部分をはき違えて、自分の人生を生きることにオッケーが出せないでいるお母さんは多いのかもしれません。
日付:2018年2月13日 カテゴリー:日々の雑記
なぜ「気づいたら5キロ太っている」のか?
お正月に「ついつい食べ過ぎて」体重が気になっている、という方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに私は、子どもたちとずっと一緒にいたので食べ過ぎる暇もなく、というかまともに食事をとる暇もなく・・・
患者様の中には、「気づいたらここ1年で5キロも増えていました」「特に食べている量は変わらないのに体重が勝手に増えているんです」という方もいらっしゃいます。特に更年期世代の方は「ずっと食べる量は変わらないのに・・・」という方も多いのですが、実は「食べる量が変わらないから」太るんです。
体重は勝手には増えません。体重が増える原因となる「何か」を自分が行っているから、結果として体重を増やしているだけです。「気づいたら」「勝手に」と認識しているのは、特に「食べすぎている」という自覚がないからだと思われます。
体重1キロを増やすのに必要はカロリーは約7000キロカロリーです。仮に1日100キロカロリーずつ取りすぎたとしましょう。その状態を70日間継続すれば1キロ体重が増えるのは分かりますよね?じゃあ、同様に365日継続したら、何キロ増えますか?あら不思議、上記の「気づいたら増えている体重」と一致しませんか?
100キロカロリーは、ご飯にすると普通のお茶碗に6分目くらいの量です。一言で言うと「ほんのちょっとの食べすぎ」くらいの量です。でも、その「ほんのちょっと」のカロリーオーバーを1年間続けると、結果はしっかり出るわけです。逆もしかり。夕食のご飯を子ども用のお茶碗に変えるだけで、1年で3キロ程度の減量は「いつのまにか」できてしまうのです。
基礎代謝と呼ばれる、「寝ていても消費するカロリー」は年齢とともに低下していきます。多くの女性は、年齢とともに日常的な運動量も減っていきますので、基礎代謝も落ちて運動によるカロリー消費量も落ちているのに、食べる量が「変わらない」とどうなるか、もうお気づきでしょうか?
基礎代謝が落ちたぶん運動量を増やせばいいと考えるかもしれませんが、運動で消費できるカロリーは実は微々たるものです。もちろん、運動によるインスリン抵抗性の改善など、カロリー消費以外の効果も大きいので、運動することに意味はとてもあります。ただ、「運動した分食べても大丈夫」と思っていると、結果としてはカロリーオーバーになることの方が多いので要注意なのです。
もし、あなたが「気づいたら体重が増えている」と思ったら、まずは体重が「増えた」のではなく、体重を「増やした」のだということを自覚しましょう。
その上で、上記の「ちょっと」をどちらに積み重ねていくのかを選択してみることをお勧めします。
日付:2018年1月15日 カテゴリー:日々の雑記
いつまで他人の人生を生き続けますか
クリニックには、明らかな婦人科の病気以外の「何となく不調が続く」という方もいらっしゃいます。20代や30代だと「PMSかもしれない」、40歳以上だと「更年期かもしれない」と思って婦人科を選んでいらっしゃるのですが、よくよく症状を伺ってみるとPMSや更年期障害ではないですよ、というケースの方が多かったりします。
典型的なPMSであれば、月経1~2週間前から心身の不調が出て生理がくるとスッキリよくなるのですが、「なんとなくの不調」の方は生理前にイライラや情緒不安定やめまい・吐き気などの症状が強くなるけれど、生理後も何となく軽い症状は続きます。両者を見分けるには、基礎体温とともに症状の変化を記録してみるとはっきりします。
更年期の「ような」症状を訴えてくる方の中には、甲状腺機能異常や血糖コントロールの異常や心身症・不安神経症・うつなどのメンタル疾患が隠れていることがしばしばあります。血液検査でホルモン異常やその他の内科的異常がないかを確認しつつ、症状が出ている根本的な原因を探っていきます。
原因は人によってさまざまなので、一概には言えませんが、PMSのような症状を訴える方や更年期世代の方に多い特徴が「自分の人生を生きていない」という点です。
自分のやりたいことが分からない、または自分のやりたいことや自分のケアは「後回し」にして、常に人の世話ばかりしている。あるいは、親や上司の評価を気にして「認められる」ことを目標にして行動していたり、もっと広く「他人の目」を気にして人に気をつかってばかりで自分らしい生き方ができていない。そんな方が圧倒的に多いのです。
例えば、親の評価を気にして本当にやりたい仕事につかず「親が喜びそう」な会社に就職したり。子どもの受験に親が必死になりすぎて、送り迎えや夜食の準備など自分の疲労の原因をわざわざ作り出していたり。介護に時間をとられて自分がやりたいことをできずに日々不満ばかり言いながら過ごしていたり。
これらはすべて「他人の人生を生きている」状態です。人は「本来の自分の生きたい姿」からずれると「病気」という状態になります。体や心が、「このままの方向で進むのは嫌だ!!」とサインを出しているのです。サインに気付こうとせず、それらの不調を薬で抑えこんで他人の人生のまま生きていると、もっと重大な病気になったり、重大な出来事が起きたりします。
あなたは他人の顔色をうかがいながら、他人の人生を生き続けますか?それとも、誰に何と言われようと、人の目なんか気にせず自分のやりたいことをやって言いたいことを言って「自分の人生」を生きますか?
★「健康でしかいられなくなる7つのステップ」無料配布中
PDFファイルのダウンロードになります→無料ファイルダウンロードはこちらから
★薬を使わず病気をやめる方法や妊活カウンセリングも承っております。
カウンセリングをご希望の方は、メールかお電話でお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先:045-440-5577(予約専用電話) info@vivalita.com
子宮頸がんワクチンの「被害者」であり続けるデメリット
前々回の記事で、子宮頸がんワクチンのせいで歩けなくなった・勉強ができなくなったなどの多彩な症状を訴えている状態が、実はワクチンとの因果関係はないといことをご説明しました。「ワクチンのせいではありません」と言うと、症状が出ている方がかわいそうではないかという声も聞こえてきます。でも、本当はワクチンは関係ない症状に対して「ワクチンのせいである」という思い込みを持ち続けることの方が、患者様ご本人のためにならないのです。
現在「被害者の会」という立場で、主に接種した本人ではなくその親が中心となって「この症状はワクチンのせいであると認めろ」という訴えを起こしています。しかし、前述の通り因果関係はありませんので、おそらく国も製薬会社もその訴えを認めないでしょう。そうすると、「ワクチンのせいであると認めさせる」ために、現在出ている症状が改善しないという事態が起きてくるのです。なぜなら、症状がなくなったら訴え続けることができなくなるからです。ワクチンのせいにし続けるためには、「症状がある方がメリットがある」状態になってしまっています。しかも、症状が出ている本人と、訴えている人が異なるため、代理ミュンヒハウゼン症候群とよく似た親子関係になっていく可能性があります。
これは、心理技術的アプローチで解析すれば、ごく単純なからくりです。被害者の会の方たちにとっては、被害者であり続けることに意味がある、という状態になってしまっているのです。なので、本来は症状が出て苦しんでいるご本人が一日も早く回復して元気になることが大切であるはずなのに、「ワクチンのせいである」と認めてもらうことが第一目標にすり替わってしまっています。「ワクチンのせいである」と言い続ければ言い続けるほど、症状は治らないということになってしまうのです。
また、「ワクチンのせいである」つまり、自分の責任ではなく誰かまたは何かの責任であると解釈することを「他者原因」と言いますが、病気は他者原因のままでい続けると治りません。また、ワクチンのせいにし続けるということは、そのワクチンを接種させた誰かまたは自分を責め続けることになります。「罪悪感」を持ち続けることも、前に進むことを阻む大きな足かせになります。「罪悪感は正義の仮面をかぶってやってくる」と言います。罪悪感を持ち続けると、まるで問題解決に向けて一生懸命になっているような錯覚に陥るのです。実際は、罪悪感は本来の問題から目をそらすための隠れ蓑にしかなりません。
このように、本当はワクチンのせいではない症状に対して、「ワクチンの被害者」という立場をとり続けることに、患者様ご本人対するメリットは何もないのです。
私が、ワクチンの副反応に対する「でっち上げ」を見て一番気になったのはこの点でした。このままでは「被害者」扱いされている方たちがいつまでたっても救われない。自ら治る力までも奪われてしまう。それどころか、何の根拠もない治療を色々試されて、さらに「病人」に仕立て上げられてしまう。そう感じています。
症状が出ている方にとって最も大事なことは何なのか、もう一度ニュートラルな立場に立って考えてみる必要があるのではないでしょうか。
日付:2017年10月12日 カテゴリー:HPVワクチン,子宮頚がん,日々の雑記
「子宮頸がんワクチンで不妊になる」はウソ!
前回の記事で、「副反応だ!」と騒がれている症状が実は子宮頸がんワクチンのせいで引き起こされるものではないということはご理解いただけたと思います。
これ以外にも、子宮頸がんワクチンが広く広まるのを阻んでいると思われる、いくつかの「デマ」があるのです。
例えば、最近見かけるようになったのが、このワクチンが「劇薬」に分類されていることを強調した「反対論」。ワクチンの添付文書の画像を貼り付けて、「劇薬」と書かれていることを指摘して「こんな危険な薬です」と訴えているわけですが、薬剤の分類つまりどんな薬品を「劇薬」とするかは明確な定義があります。なので、その定義に当てはまればどんな薬品も「劇薬」なのです。
例えば、心臓の病気などの時に使う「ジゴキシン」という薬の添付文書を見れば、子宮頸がんワクチンと同じように「劇薬」の文字が印字されています。でも、この薬によって病気が改善している人もいます。投与量を間違えば、危険な症状が出る可能性もあります。だから「劇薬」と分類して医療者側が取り扱いに注意しましょうと促しているわけです。「劇薬」は、必ずしも「人体に害を及ぼす危険な薬」といういうわけではなく、使い方に注意が必要な薬剤であることを示しているのです。
また、以前から医学的には何の根拠もないなと感じながらも、あまりにもよく目にする「反対論」が「子宮頸がんワクチンで不妊になる」というデマです。こんな意味不明の指摘が出てしまった大元は、南出喜久治氏のYouTube動画「サーバリックス子宮頸がんワクチンによる民族浄化/弁護士 南出喜久治」なのだそうです。ワクチンに含まれている「アジュバント」という成分が、動物の避妊治療(去勢)に使われる薬剤にも含まれているので、子宮頸がんワクチンは「不妊にさせるワクチンだ」というこじつけ論が展開されているのです。
「アジュバント」は多くのワクチンに含まれている成分です。これは、ワクチンの効果を賦活化(少量でも効きやすくする)するために、ワクチンとしての有効成分と合わせて配合されるものです。子宮頸がんワクチンは、HPVというウイルスに対する免疫抗体を作るためのものです。なので、この抗体を作りやすくして、なおかつ定着しやすくする目的で「アジュバント」が入っています。一方、避妊用のワクチンには「妊娠しなくするための成分」が入っており、その作用をサポートするために「アジュバント」が一緒に含まれています。要するに「アジュバント」が避妊効果を発揮するのではなく、あくまで「妊娠しなくするための成分」の作用をアジュバントが増強しているに過ぎないのです。子宮頸がんワクチンには、そもそも妊娠しにくくなる成分など入っていませんから、それがアジュバントを加えたからと言って「不妊になる」わけではありません。
おかしなデマのからくりがご理解いただけましたか?
ワクチン接種後の妊娠率については、接種した人と接種していない人で差がないというデータは出ています。もちろん、日本では接種開始後の年数が短いので、妊娠に対する影響について「日本人だけで」とったデータはまだありませんが、世界中で同じような内容の研究はされており、妊娠に対しては何も影響がなことがハッキリしています。
また、デンマークのコホート研究では、妊娠中にこのワクチンを接種した場合の安全性について研究したデータがあります。主要な先天性異常・自然流産・早産・死産・低体重出征・発育不全などの項目について、ワクチン接種した人と接種していない人を比較した結果、両者に有意な差はなかった、つまり妊娠転機にリスクの変化はないという結論が出ています。
詳細を知りたい方は、論文を参照してくださいね。
N Engl J Med 2017;376:1223-1233
このように、子宮頸がんワクチンを「危険なものである」と指摘する理論は、いずれも医学的には根拠がなかったり単なるこじつけだったりします。ネットや雑誌に載っているこれらのデマをうのみにして、本来予防できるはずのがんを予防しないことが賢明な選択なのかどうかは、各自がしっかり考えるべきだと思います。
「子宮頸がんワクチンで不妊になる」よりも、子宮頸がんになって子宮を失う方がよほど確実に妊娠の機会を失います。私は少なくとも、自分の娘にそのような思いはさせたくないと考えます。
どの情報が正しいのか、誰が言っているのかが正しいのかよりも、どのような選択をすることがトータルで見た時に「すべての女性の健康サポート」につながるのかを考えてこれらの情報をお伝えしています。
あなたや大切な人の未来を守るお役に立てていただければ幸いです。
日付:2017年10月10日 カテゴリー:HPVワクチン,子宮頚がん,日々の雑記
子宮頸がんワクチンの安全性
今日は避妊教育ネットワークの勉強会に参加してきました。他のメンバーの活動報告に刺激を受けたり、ピルによる避妊機序について生理学的に詳しい解説を受けたり、子宮頸がんワクチンの接種がなぜ広まらないのかについて日本の現状の裏話を聞いたり、盛りだくさんの内容でした。
子宮頸がんワクチンの接種は、公費負担での接種が開始されてからもそれほど希望者が多くなく、「なぜこれほどまでに予防意識が広まらないのだろうか」と懸念していましたが、「積極的接種を推奨しない」との発表後は全くと言っていいほど接種希望者がいらっしゃらなくなりました。
でも、10代の娘さんを持つお母さまからは時々質問を受けたりします。特に、お母様ご自身が子宮頸部の異形成で定期フォローを受けていらしたりすると、「娘には同じ思いをさせたくない」というお気持ちもあるようです。ワクチン接種を受けさせたいけれど、メディアの報道を見ていると怖くなるという意見が多いため、まずはメディアの報道をどのように受け止めたらよいのかを解説していきたいと思います。
私自身は、明らかにそうであるというエビデンスのある内容についてはそのエビデンスを優先します。その事実を証明または否定するエビデンスが充分でない時は、「エビデンスがないからそれは間違いだ」とは断定せず、その事実が本当である可能性も考えるようにしています。
子宮頸がんワクチンに対して「積極的接種を推奨しない」という措置をとらざるを得なくなった背景には、メディア上で報道されているようなけいれんなどの激しい症状を伴う「副反応」が見られるとの指摘を受けたせいです。しかし、実際は、この問題となっている症状とワクチンの因果関係についてははっきりと否定されているのです。学会も、WHOも、明らかな因果関係はないと結論付けているにもかかわらず、まるでワクチンのせいでそのような症状が出てしまっているような取り上げられ方がされているため、一般の方は「ワクチンの副反応であんなふうになってしまうこともあるのか」と誤解をしてしまっても無理はありません。
どんな薬もそうですが、大人数に使えば一定の割合で「副反応」と呼ばれる症状が出ることがあります。ワクチンの副反応もそうですが、接種後に出た症状が「明らかにワクチンのせいなのか」を見極めるには、いくつかポイントがあるのです。
1)症状がワクチン接種後のみに見られて接種前には見られない
2)ワクチンを打っていない人に同じ症状は出ていない
3)ワクチンの接種以外ことで同じ症状が出ていない
4)ワクチン接種と症状の出現時期に明らかな因果関係がある
例えば、ワクチンを接種した数分後に失神するケースはあります。医学的には「迷走神経反射」と呼ばれるもので、一時的に血圧が下がって急に意識を失うものです。ワクチンを接種してすぐに起きるものなので「ワクチン接種のせいでそうなった」と言えますが、実は同じことは採血でも他の注射でも起こりえます。なので、この場合3)の「ワクチン以外のことで同じ症状が出ない」に当てはまりません。つまり、「ワクチンという薬剤の成分」で起こった症状ではなく、「注射という痛み刺激」のせいで起こった症状ということになります。
子宮頸がんワクチン接種後に起きているとされる、けいれんや歩行ができなくなるなどの多彩な症状は、ワクチンを接種していない人や男性にもみられていること。ワクチン接種が開始される前から、同様の症状を訴える人がいたことなどから、ワクチンの薬剤そのものが影響して引き起こされた症状ではないという結論に至っているのです。
ワクチン接種後から症状が出た場合に、ワクチン接種という痛みや心理的負担が「引き金」になった可能性は考えられるかと思われます。でも、それは「薬剤」のせいではないわけです。その点が、最も大きな誤解として、一般の方には「副反応だ!」と印象つけられているのではないかと感じました。
実際、「海外のデータではあてにならない。日本人特有の反応の仕方があるのかもしれない」との指摘を受けて、名古屋市が接種した人としていない人に見られる症状を、正しい統計学的分析をして比較したデータがあります。倦怠感等のいずれの症状もワクチンを接種したグループの方が「わずかに少ない」という結果が出ているとのことです。つまり、「副反応だ」と指摘されている症状は、実際はワクチン接種が関係ない可能性が大きいのです。
日付:2017年10月9日 カテゴリー:子宮頚がん,日々の雑記